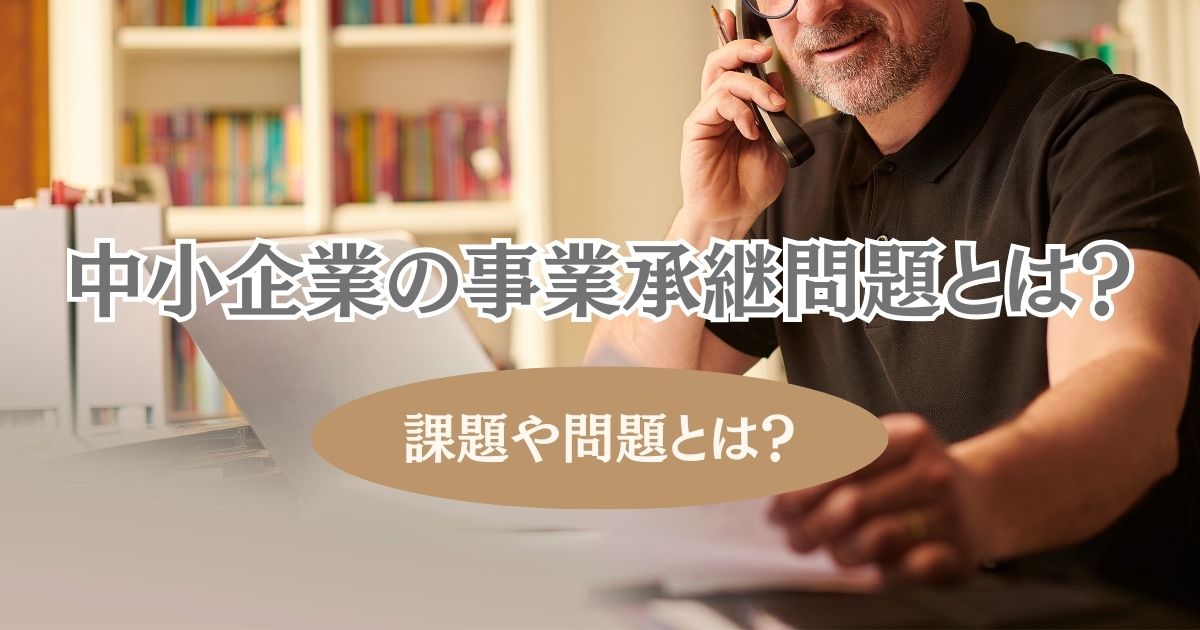中小企業の事業承継は、会社の未来を左右する重要な経営課題と言えます。
とはいえ「具体的に何から手を付ければいいのか」「自社の本当の課題は何なのか」は、つかみにくいのではないでしょうか。
この記事では、事業承継のプロセスで実際につまずきやすい問題点を体系的に整理し、準備が遅れたときのリスクや解決への道筋を徹底的に解説します。
実務に直結する準備手順や家族・関係者との合意形成のコツ、そして現場目線の成功事例を中心にお伝えするので、一歩踏み出すきっかけにしてもらえると幸いです。

目次
この記事を監修した弁護士
西田 幸広 法律事務所Si-Law代表
弁護士・法律事務所Si-Law/(株)TORUTE代表・西田幸広 熊本県を中心に企業顧問70社、月間取扱160件以上(2025年8月時点)。登録3,600社・20超業種を支援し、M&A・事業承継を強みとする。弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士の資格保有。YouTubeやメルマガで実務解説・監修/寄稿多数。LINE登録特典で「事業承継まるわかりマニュアル」提供。
中小企業の事業承継問題とは?
中小企業の事業承継では、次のような重要な問題が同時並行で動いていきます。
- 人(候補者・体制)
- 資金(取得・運転)
- 税務・法務(相続・契約)
- 関係者調整(従業員・取引先・金融)
親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)のどの方法を選ぶにしても、「何を・いつ・誰に・どの基準で引き継ぐか」を早い段階で明文化し、年次計画へ落とし込むことが肝心と言えるでしょう。
曖昧さを残すほど判断は遅れ、現場の迷いも増えてしまいます。
まずは要所を言葉にし、工程と期限を設定していくのがおすすめです。
社内外の不安や憶測は多くの場合、「情報の不足」から生まれるため、全体像がひと目で分かるロードマップを可視化し、定期的に進捗を共有しておきましょう。
具体的に、中小企業の事業承継で現れやすい問題には、以下のようなものがあります。
- 後継者が不足している
- 後継者の育成不足
- 事業承継のための資金不足や準備の遅れ
- 事業承継を相談する相手がいない
- 相続トラブルの発生
- 取引先・従業員からの反発
- 経営者自身に退く意思がない
ここから、これらの問題点と解決するための方法を解説します。
後継者が不足している
後継者不足の問題は、少子高齢化と都市集中で候補が減っている現状などが大きく取り上げられがちのように思えます。
ですが実際には、会社側の「情報の非対称性(持っている情報を見せないこと)」や、「魅力の非可視化(事業の魅力が外から見えないこと)」などの問題点が重なることでも、生じやすくなっています。
対策としてまずは、後継者採用の発想で自社の魅力を棚卸しするのがよいでしょう。
強み・成長余地・柔軟な働き方の設計・権限移譲の計画までを言葉に落とすと、候補者の目に届きやすくなります。
そして、社内と社外の両方で候補者を同時に増やしていきましょう。
社内では将来像を開示し、小さな権限移譲を繰り返して意欲のある人材を育成しておくのがおすすめです。
社外では、事業承継・引継ぎ支援センターや民間マッチング・金融機関・士業ネットワークを活用し、接点を増やします。
ただし、理想像に合致する人を最初から求め過ぎないことも大切です。
後継者不在の現状や後継者不在率については、以下の記事でも解説しています。
関連記事:事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!
後継者の育成不足
後継者がいても育成不足となれば、経営者は安心して事業を任せられず、承継に不安を感じてしまうのではないでしょうか。
そのためには、見つかった候補者に「任せられる状態」を作らなければなりません。
この場合、1〜2年という期間をかけて、権限とKPI(重要業績評価指標)を段階的に移す設計にしていくのがおすすめです。
営業や現場、経理や人事の判断は、順を追って少しずつ任せていくようにすると、無理がなく失敗も減らせるでしょう。
また並行して、金融機関や主要顧客への顔出しを早めに始め、社外の信用を丁寧に引き継げるように進めていきます。
経営者が持つ「経験に基づく知識」を、業務標準書・チェックリスト・トラブル事例集に落とし込み、共有資産として残しておくとよいでしょう。
さらに、承継後の統合(PMI)を視野に、役職・評価制度・会議体の更新日をあらかじめ定めておくこともポイントになります。
育成を人事制度と一体で運用することで、任せる側と任される側の迷いを減らし、移行の質を高められるはずです。
事業承継のための資金不足や準備の遅れ
事業承継では、株式取得や役員退職金・承継後の運転資金・専門家費用まで、多様な資金需要が一斉に立ち上がります。
そのため、資金不足やそれにともなう準備の遅れが出てしまう可能性が考えられます。
まずは簡易的な企業価値評価(バリュエーション)を実施し、必要総額を洗い出しましょう。
次に、内部資金・借入・補助金を比較し、資金の使い道と時期をスケジュール化すると、交渉の選択肢が広がります。
決算の磨き上げや余剰資金の確保を、先行させておくのがおすすめです。
着手が遅れるほど好機は痩せ細る可能性があるため、原則として「評価→資金計画→条件交渉」の順で段取りを整えることを意識してください。
事業承継を相談する相手がいない
事業承継では、専門家へ相談することが大切になりますが、「誰に相談すべきか」が曖昧だと次の段階へと進みにくくなってしまいます。
そのために、専門家の役割を整理すると迷いが減るでしょう。
| 税理士 | 税務対策・決算・株価評価 |
| 弁護士 | 契約の整理・相続や紛争の予防 |
| 仲介会社・FA(ファイナンシャル・アドバイザー) | 相手候補の探索・条件交渉 |
| 公的センター | 初期相談・公的制度(補助金など)の案内 |
まずは公的窓口で全体像を押さえ、次に守備範囲が明確な専門家を役割ごとに集めて小さなチームを組むのがおすすめです。
体制ができたら情報管理の中枢を一人に定め、議事録・タスク・期限を一元管理することで、意思決定の速度を高められるでしょう。
あわせて、利益相反を避ける設計も欠かせません。
支援内容・成果物・費用は必ず文書化し、合意の順序を「NDA→基本合意→個別契約」と段階化しておくことをおすすめします。
契約前に期待値をすり合わせておくことで、後戻りを減らせるでしょう。
相続トラブルの発生
事業承継における親族間の財産配分は、トラブルが発生しやすい領域と言えるでしょう。
トラブルを避けるためには、以下の手順で進めるのがおすすめです。
1.暫定評価
会社の暫定的な価値を評価する
2.分配案の比較
贈与・売買・相続といった複数の方法を比較し、最適な分配案を作成する
3.年次シミュレーション
納税時期と資金繰りを年ごとに描いて、無理のない運びを確かめる
遺留分(一定の相続人に法律上保障される遺産の最低限の取り分)の影響や納税のタイミングは、早めに家族全員で共有するようにしましょう。
現金・生命保険・不動産を組み合わせ、偏りを平準化しておくのがおすすめです。
議論を円滑にするために家族会議の議題・論点表・意思決定基準を事前配布し、争点を「誰が」ではなく「どう設計するか」へ移すことがポイントになります。
会合後は議事録を残し、最終合意書まで整えると、後日の誤解を大きく減らせるはずです。
また、専門家同士を同席させ、相続・契約・評価の前提を一枚の表に統合すると、家族が納得できる案の幅が確実に広がります。
段取りを丁寧に重ね、合意形成を計画的に進めていきましょう。
取引先・従業員からの反発
経営者の交代によって取引先や従業員が不安を感じている状態を放置すると、反発はもちろん、人材の流出や取引の離反といった大きな問題につながる可能性があります。
この不安を解消するために、まずは情報発信の「質と頻度」を高め、段階的に説明する姿勢を貫くのがよいでしょう。
承継の目的・新しい経営方針・雇用や処遇の考え方・主要プロジェクトの継続可否を順序立てて伝えることがポイントです。
社内には、評価の物差し・任せる範囲・将来のキャリアを具体的に示し、いつ何を渡すかの権限移譲計画も一緒に共有することで、モチベーションが保ちやすくなります。
取引先には、支払い・品質・納期を守るための具体策を書面で示し、担当責任者の連絡先もはっきり伝えておきましょう。
何を守り・何を変えるのかをはっきり言葉にすると効果的です。
例えば「品質基準・サービス水準は維持する」「効率化や新商品は進める」といったように、区分して伝えるのがよいでしょう。
経営者自身に退く意思がない
長年情熱を注いで築き上げてこられた事業を手放すことへの迷いや不安があるのは、当然のことだと思います。
しかし、経営者が意思決定を先延ばしにするほど事業承継は難しくなり、リスクも大きくなっていく可能性が考えられます。
まずは「事業のこと」「財産のこと」「これからの人生のこと」、この3つを切り離さずに考えてみることが大切です。
そして、次の世代に託す決意をご自分の言葉で表現してみてください。
また、健康問題や突発事象による緊急承継を想定しておくことも必要になるでしょう。
関係者や専門家の力も借りながら一歩を踏み出すことで、新たな道が見えてくるはずです。
事業承継できなかった場合のリスク

事業承継が進まない状況を放置すると、顧客・従業員・取引先・地域社会との信頼関係が分断され、企業の競争力はじわじわと蝕まれていくことになります。
金融機関の支援姿勢も、具体的な承継計画の有無によって明暗が分かれると言えるでしょう。
だからこそ、計画を早期に整え、社内外へ段階的に示しておくのがおすすめです。
もしも事業承継できなかった場合には、以下のようなリスクに直面することが考えられます。
- 廃業や倒産に追い込まれる
- 従業員の雇用喪失
- 地域経済への悪影響
- 技術やノウハウの散逸
- 顧客や取引先への影響
それぞれについて、詳しく解説します。
廃業や倒産に追い込まれる
突然の病気や事故で経営に空白が生じると、資金調達や大型受注が滞り、廃業・倒産リスクが跳ね上がります。
まずは、事業継続の「停止線」を先に定めておくのがよいでしょう。
そしてそのラインに至る前に、与信枠の確保や借換えなど資金面のセーフティネットを用意するのがおすすめです。
外部支援の導入手順と、社内キーマンによる役割代替も事前に明文化しておきます。
さらに、承継案と計画的撤退案を同じ条件でシミュレーションし、判断の質を磨きましょう。
こうした備えが損失の最小化につながり、従業員や取引先の納得も得やすくなるはずです。
従業員の雇用喪失
会社の将来像が曖昧なままだと従業員の不安が募り、離職も進みやすくなります。
まずは従業員が「ここで働き続ける理由」を言語化できる状態を整えましょう。
最初の段階から、待遇の方針・身につけるスキルの一覧・具体的なキャリアの道筋を見せておくのがおすすめです。
あわせて、評価制度を新しくする方針と、教育に力を入れる計画を早めに伝えると、安心して働ける空気が生まれるでしょう。
加えて、ロールモデルを示し、権限を渡す時期の予定を全員にわかる形で共有しておくのがおすすめです。
誰もが見て確認できる承継ロードマップを用意し、後継者への権限移譲を早期に進めるようにしましょう。
この二本柱が雇用を守る最良の防波堤となり、組織の納得と定着を後押ししてくれるはずです。
地域経済への悪影響
中小企業は単なる一企業ではなく、地域の雇用・税収・暮らしを支えるサービスの基盤とも言えます。
しかし一社の停止が起こると、仕入れ・物流・設備保守まで波紋が広がり、取引先の各所で障害が連鎖しかねません。
なかでも代替の難しい地場産業では、影響が深刻化しやすいでしょう。
この連鎖を断つには、事業を「地域のインフラ」と位置づけ、地域ぐるみで守る視点が大切です。
自治体・金融機関・支援機関と早期に連携し、共同受注や設備の共同利用、広域でのM&Aマッチングを設計・実行しておくのがおすすめです。
加えて、役割分担と連絡経路を先に定義し、普段から少しずつ試していく運用を重ねるのがよいでしょう。
関係者が同じ地図を持てば、いざという局面でも機動的に動けるはずです。
こうした連携が、地域に事業を残す鍵になります。
技術やノウハウの散逸
熟練者が長年培ってきた加工条件・作業の段取り・独自の営業術といった技術やノウハウは、記録に残さなければ引退と同時に失われかねません。
ノウハウを個人ではなく仕組みに埋め込み、誰が担当しても再現できる体制を整えるのがおすすめです。
承継を待たずに工程標準書・品質指標・トラブル事例集を整備し、動画・写真・図解などで可視化しておくとよいでしょう。
あわせて、熟練者と若手が互いに学び合う「逆メンタリング」を導入すると現場の知恵とデジタル活用がかみ合い、技術承継の速度と品質を高められるはずです。
こうした積み重ねが技術やノウハウの散逸を防ぎ、組織としての競争力を長期に維持する土台になります。
顧客や取引先への影響
経営者交代の局面では、顧客や取引先は品質・納期・価格に不安を抱きがちです。
この不安を放置すれば取引継続が揺らぐ恐れがあるため、主要顧客には個別訪問をおこない、新体制・責任者・品質保証の方針を明確に伝えるようにしましょう。
あわせて、どの水準までサービスを守るのか・増産やカスタム対応が可能かを、数字や条件でわかるように伝えることで、実行力への不安が和らぎます。
価格改定が避けられない場合は、原価構造の内訳とコスト削減の施策をセットで開示し、合理性を丁寧に説明することが大切です。
さらに、「これまでと変わらない点」と「より良く変えていく点」の境界を言葉と数値で可視化するのがおすすめです。
先回りの説明と検証可能な指標の提示、定期的な進捗共有をおこなうことで、信頼維持の近道となるでしょう。

中小企業の事業承継の方法と課題
中小企業の事業承継の主要ルートは、親族内承継・従業員承継・M&A(第三者承継)の3つです。

どの方法を選ぶにしても、共通して重要になるのは「早期の計画策定」と「関係者との調整」だと考えます。
税務・法務・金融を横断して設計し、後継者の育成と対外発信を並走させる体制を整えるのがおすすめです。
まずは自社の強み・弱み・将来性を率直に棚卸し、「絶対に守る価値」と「条件により譲れる範囲」を文章で定義しておくとよいでしょう。
そのうえで各承継方法の課題を事前に比較し、いずれの選択肢でも直ちに実行へ移せる準備状況を作ります。
判断の先送りを避けるため、意思決定の基準・期限・担当を明記し、定期的に進捗を検証しましょう。
ここから、各ルートの具体的な内容と課題、そして実行の流れを解説します。
親族内承継
親族内承継とは、会社の経営権を現経営者の親族に引き継ぐことです。
この方法の最大のメリットは、経営理念を受け継ぎやすく、従業員や取引先にも安心感を与えやすい点にあると考えます。
一方で、候補者の適性・相続調整・株式取得や納税にともなう資金などが課題になりがちです。
成功率を高めるため、次の対策を段階的に進めましょう。
・早期の意思確認と育成
後継者候補の意思を早めに確認し、現場・財務・対外折衝を含む育成計画を具体化します。
権限移譲のスケジュールも併せて設計するとよいでしょう。
・財産分配の合意形成
株式や資産の分配方針を家族で合意し、遺留分や納税負担の影響を年次シミュレーションで可視化します。
生命保険・持株会社・資本政策の選択肢を比較検討するのがおすすめです。
・記録の活用
家族会議の議事録を継続的に作成し、決定事項と理由を残すことで誤解や紛争の予防に繋がります。
従業員承継
従業員承継は、会社の経営権を自社の役員や従業員に引き継ぐ方法です。
現場や事業への理解が深く、組織への適応が速い点が大きな強みと言えるでしょう。
その反面、株式取得のための資金準備と、新体制に適した経営管理体制の整備が課題になりがちです。
候補者が複数いる場合は、権限と責任の割り振りを先に合意しておくと後の混乱を避けられるでしょう。
成功の確率を高めるには、持株会の活用や役員退職金の設計、外部取締役の起用で統治体制を強化するのがおすすめです。
動機付けは金銭報酬だけに偏らせず、やりがい・裁量・成長機会も組み合わせると効果的です。
就業規則や評価制度を見直し、新リーダーが権限を発揮しやすい環境を整えることで、組織全体を新体制のルールとビジョンへ自然に寄せていけるようになります。
資金面の段差については、後継者の株式取得や運転に必要な資金計画を早期に作成し、金融機関や投資家の関与を得るとよいでしょう。
条件を比較検討し、返済計画と併せて社内外へ丁寧に説明しておくと、信頼を損なわずに移行を進められるはずです。
M&A(第三者承継)
M&A(第三者承継)は、会社を外部の企業や個人に売却したり、合併したりすることで、経営権を引き継ぐ方法です。
買い手の資本・人材・販路を活かせるため、成長と存続の両立が期待できます。
まず、人材・技術・顧客基盤など自社の「価値の源泉」を洗い出し、魅力を言語化しておきましょう。
交渉では売却価格だけに偏らず、雇用の維持や事業拠点・社名の扱いなど「価格以外の条件」も挙げることで、これまでの事業の価値観や方向性を守りやすくなります。
支援を依頼する専門家は、費用体系・利益相反の管理・情報管理体制を比較し、担当者の実績まで確認してから選定するのがおすすです。
買い手には、クロージング後の統合計画(PMI)の事前提示を求めましょう。
役割分担・意思決定フロー・初期100日の施策が示されていれば、社員の不安が和らぎ、移行がスムーズに進むはずです。
価値の見える化・条件の多面的設計・統合計画の先出しが、準備のポイントと言えるでしょう。
中小企業の事業承継問題の解決策は?

中小企業の事業承継問題の解決策として、ここでは以下のポイントをご紹介します。
- 早めに事業承継を検討する
- 複数の選択肢を検討する
- 従業員や相続人への配慮を意識する
- 経営状況や財務状態を明確化しておく
- 国や自治体の制度を利用する
- 信頼できる専門家を探して相談する
動き方を具体化して解説するので、参考にしてください。
早めに事業承継を検討する
事業承継を進める第一歩は、時間を味方につけること、と考えます。
承継は人材・資金・関係性を編み直す大規模プロジェクトであり、少なくとも1~2年を要します。
健康不安や市況変動、資金調達の不確実性が高い今こそ、着手の速さが最終的な選択肢を広げるでしょう。
実際には、以下の手順で計画を進めるのがおすすめです。
- 現状診断:事業・財務・人材・法務・税務を総点検する
- 目標設定:誰に・いつ・何を引き継ぐかを定義する
- 実行計画:関係者の役割・期限・達成指標を確定する
あわせて、社内外への発表タイミングを計画に組み込みましょう。
情報を先回りして伝えることで、不安や憶測を抑えやすくなります。
複数の選択肢を検討する
事業承継は特定のルートに早々に絞り込まず、複数の選択肢を並走させておくのがおすすめです。
親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)の三つのルートを並行で設計し、どれが走ってもよい体制を整えましょう。
例えば、社内の後継者育成を進めつつ、同時にM&Aの市場調査や外部候補の探索準備も進行するなどという流れになります。
そのなかで判断する基準は、継続性・雇用・価格・スピード・文化適合の5点で揃えると整理しやすくなるはずです。
専門家や主要関係者の意見も広く取り入れながら、最終判断は経営者自身がおこない、責任の所在を曖昧にしないようにしましょう。
従業員や相続人への配慮を意識する
事業承継の成功は、最終的に関係者一人ひとりの納得にかかっていると言えます。
そのため、従業員や相続人への配慮は欠かすことができません。
まず従業員には、新体制での処遇方針と具体的なキャリアの見通しを提示しましょう。
安心材料を先に示すことで、不安の連鎖を抑えられます。
相続人には、会社評価の基準と財産分配の透明性を丁寧に説明しておくとよいでしょう。
また運営面では、関係者ごとに「意見を聴く場」と「決定事項を伝える場」を意図的に分け、想定問答(FAQ)や社内規程を整えて、小さな成功事例をこまめに共有すると信頼の積み上げが一段と進むはずです。
さらに、議事録の作成と決定事項の公開範囲をあらかじめ定めることで情報管理の境界が明確になれば、誤解や不必要な風評を未然に防げます。
こうした基本動作を丁寧に重ねることが、合意形成の最短距離につながるでしょう。
経営状況や財務状態を明確化しておく
後継者・金融機関・M&Aの買い手は、共通して「見える化された数字」を重視します。
そのため、自社の経営状況と財務状態を早めに整えておくのがおすすめです。
各部門の売上や利益、お客様ごとの収益など、重要な数字を一覧で見られるようにしておくと、会社の状態を素早く把握できます。
特定顧客や単一事業への依存を是正し、月次決算の精度を高めれば、外部からの評価は自然と上がります。
さらに、必要に必要に応じて税理士や会計士などの専門家に会社の状態を確認してもらうことも検討してみてください。
数字の信頼性が高まれば、後継者や関係者からの信頼も高まり、話し合いが進めやすくなります。
その結果、事業承継全体がスムーズに運ぶようになるはずです。
国や自治体の制度を利用する
事業承継で活用できる公的制度は、事業承継税制(納税猶予・免除)・信用保証・各種補助金・専門家派遣・公的相談窓口など多岐にわたります。
効果を最大化するには、まず全体像を押さえ、自社の段階に合うメニューを絞り込みましょう。
要件や申請期限、手続きの流れを最初に整理しておくと、判断がぶれにくくなります。
申請準備では、契約書・領収書・計画書類などの必要書類を漏れなく整え、全体スケジュールを厳密に管理しましょう。
担当部門と専門家の役割を明確にし、チェックリストで進捗を可視化しておくのがおすすめです。
なお制度によっては改定が頻繁におこなわれるため、最新情報を公的サイトで随時確認し、条件変更が生じた際は計画を速やかに更新するようにしましょう。
適切な制度選定と手続き運用ができれば、承継コストの圧縮と資金面の不確実性低減に繋がるはずです。
信頼できる専門家を探して相談する
事業承継の問題解決をスムーズに進めるには、信頼できる専門家へ早期に相談することが大切と言えます。
税理士・弁護士・社会保険労務士・司法書士に加え、M&A仲介会社・FA(ファイナンシャル・アドバイザー)・金融機関を束ねてチームを組成しましょう。
選定時は、見積もり・契約条件・成功報酬・リーガルチェックの観点を共通フォーマットで比較し、可視化しておくと判断がぶれにくくなります。
あわせて秘密保持契約(NDA)とアドバイザリー契約を締結し、機密情報の管理と役割分担を明確にしておくのがおすすめです。
承継の成否は、専門家のレスポンスの速さと情報連携のスムーズさにも大きく左右されるため、まず初期診断会議を設定し、現状の課題と優先順位を全員で共有しましょう。
実行計画・担当者・期限をまとめ、進捗を定例で確認していくようにします。
こうした整備を先におこなえば、意思決定の速度が上がり、交渉や申請の精度も高まるはずです。
そして何から・どのように進めればいいのか迷う場合は、「TORUTE株式会社」がお手伝いさせていただきますので、ぜひご相談ください。

事業承継の後継者募集はできる?
事業承継の後継者を募集するルートは複数ありますが、主に以下のような方法があります。
- 公的な支援機関を利用する
- 民間の専門家やマッチングサービスを活用する
- 士業へ相談する
後継者募集が成功するかどうかは、募集を始める前の準備にかかっていると言えます。
まず現経営者が「譲り手の覚悟」を固め、承継条件と移行計画(役割・報酬・権限移譲の時期)を整理して発信しましょう。
あわせて募集文は「引き継ぎ案内」ではなく「採用」の発想で作成すると効果的です。
求めるスキル・価値観・着手してほしい課題・期待する成果時期まで具体化しておくとよいでしょう。
これによりミスマッチを抑え、意欲の高い候補者と出会える可能性が高まります。
ここからは、後継者募集のそれぞれの方法について具体的に解説します。
公的な支援機関を利用する
まず代表的なのが、各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターや商工団体です。
これらの機関は中立の立場で地域ネットワークを持ち、初期の無料相談・マッチング・専門家・金融機関の紹介までサポートしてくれます。
自社の事情に合わせたロードマップ作成も依頼できるため、最初の相談先としても頼りやすいでしょう。
費用負担を抑えながら、守秘義務の下で安心して情報を共有できる点も大きなメリットです。
民間の専門家やマッチングサービスを活用する
スピードと候補層の広さでは、民間のM&A仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)といった専門家、マッチングサービスが有力です。
最近は、案件設計・買い手探索・条件交渉・デューデリジェンス・PMI(統合計画)までを支援してくれる事業者も増えています。
選ぶ際には、手数料体系・重要事項説明・機密情報の管理体制・利益相反の有無・担当者の実績を必ず確認し、複数社を比較して検討すると安心でしょう。
加えて、契約前に想定する支援範囲と成果物を文書で明確化しておくと期待値のずれを防げるため、承継プロセスを滞りなく前へ進めやすくなります。
士業へ相談する
税理士・弁護士・社会保険労務士・司法書士などの士業は、税務・契約・労務・登記の要所で不可欠です。
なかでも弁護士は、条件交渉・契約書作成・将来の紛争予防まで関与するため、早めに相談しておくと安心できるでしょう。
大切なのは顧問のみに依存せず、事業承継に強い実務家を見つけて案件ごとに最適なチームを組むことにあると言えます。
選定時は経験領域や担当体制を確認し、役割分担を明文化しておきましょう。
また、弁護士・税理士・会計士といった専門家に、お互いの役割分担や連絡方法、どのくらいの期間で返事をもらえるかなど、事前に取り決めておくと安心です。
情報共有の経路と期限を定めておけば、手続きの遅延を防ぎ、承継プロセスを着実に前へ進められるでしょう。
中小企業の事業承継は「TORUTE株式会社」へ

事業承継は、方針を定め・体制を整え・事業を守り抜くまでを進めていく決断の連続と言えます。
TORUTE株式会社では、経営者の想いと現実的な制約を両立させながら、実現可能な計画づくりをおこない、複雑なプロセスをすべてワンストップで支援させていただいています。
初回相談では、現状の課題診断・優先順位の整理・関係者マップの作成まで丁寧にサポートし、地域・業種に応じた専門家ネットワークとも連携します。
今なら期間限定で、事業承継に役立つ無料のマニュアルをプレゼントしています。
ぜひ参考にしていただき、まずは課題を可視化して、次の一手を具体化していきましょう。
\事業承継マニュアル無料プレゼント!/
まとめ
中小企業の事業承継にはさまざまな課題がありますが、最初の落とし穴は「見えないまま時間だけが過ぎること」と言えます。
事業承継に必要な要素はどれも時間を要し、先送りするほど選択肢が減る上に、リスクが膨らみかねません。
回避するためには、まず現状診断をおこない、親族内・従業員・第三者の各ルートを同時並行で検討することから着手しましょう。
計画を紙に書き出し、進捗を確認していく運用を取り入れることで、着実に前進できるはずです。
何から手をつければよいかわからない場合は、ぜひ一度、TORUTE株式会社にご相談いただけますと幸いです。

まずはお気軽にご連絡ください
受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)
事務所概要
熊本
熊本市東区桜木3-1-30 ヴィラSAWADA NO.6 102号室
福岡
福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F
コラム一覧
- 2026年1月14日熊本で事業承継をお考えの方!支援制度や補助金・相談先と進め方までを専門家がわかりやすく解説!
- 2026年1月14日事業承継特別保証制度とは?メリット・デメリットや要件・申請方法もまとめて紹介!
- 2026年1月7日事業承継で専門家が必要な理由は?選び方やタイミング・補助金は使えるのかも解説!
- 2026年1月7日事業承継の株式譲渡の方法は?メリットや手続き方法・税金の特例制度についても解説!
- 2025年12月31日事業承継の株価対策とは?3つの評価方式や自社株の引き下げ対策をまとめて解説!
- 2025年12月31日承継会社とは?分割会社との違いや手続き方法・メリットとデメリットもわかりやすく解説!
- 2025年12月24日事業承継補助金の対象経費は?枠組みごとのルールや金額・認められない例も紹介!
- 2025年12月24日事業承継税制の延長はいつまで?提出期限のスケジュールや緩和要件についても解説!
- 2025年12月17日事業承継補助金は親子間でも対象?要件や申請方法・利用するときの難易度も解説!
- 2025年12月17日事業承継の手順は?引き継ぐ3つの要素や必要書類・受けられるサポートもまとめて紹介!
- 2025年12月10日事業承継と相続との違いは?税制の対象や手続き方法・起こりやすいリスクも紹介!
- 2025年12月10日事業承継の税制優遇とは?制度の内容や期限・使えないケースについても徹底解説!
- 2025年11月27日事業承継の費用の相場はどれくらい?税金対策や補助金・誰が負担するのかも解説!
- 2025年11月27日事業承継と会社売却の違いは?メリット・デメリットや従業員はどうなるのかも徹底解説!
- 2025年11月27日事業承継後のトラブルで起こりやすい事例は?原因や対応策・成功例までまとめて紹介!
- 2025年11月27日事業承継の相談先10選を紹介!相談費用は無料なのか・選び方のポイントも解説!
- 2025年11月26日事業承継の企業価値とは?算出方法や3つのアプローチ・高値がつくケースも解説!
- 2025年11月26日事業承継の後継者不足の原因は?担い手がいない理由や解決策・成功例まで紹介!
- 2025年11月26日中小企業の事業承継問題とは?課題や問題点・具体例についてもわかりやすく紹介!
- 2025年11月25日事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!
- 2025年11月25日事業承継の補助金や助成金は?2025年度はいくらもらえるのか・対象経費も解説!
- 2025年11月25日事業承継の手続きで法人の場合の流れは?必要書類や税金などの費用・補助金もまとめて解説!
- 2025年11月24日事業承継に使える補助金は?2025年度のスケジュールや申請方法・対象経費なども解説!
- 2025年11月24日事業承継でやるべきことリストを紹介!必要な知識や書類・課題についても解説!
- 2025年11月24日事業承継ファンドとは?活用が有効なケースやメリット・デメリットも紹介!
- 2025年11月23日事業承継税制の要件とは?特例措置と一般措置の違いやメリット・デメリットも解説
- 2025年11月23日事業承継とM&Aの違いは?メリットとデメリットや選び方のポイント・課題も徹底解説!
- 2025年11月23日事業承継とは?基本的な考え方や支援制度・手順までをわかりやすく徹底解説!
- 2025年3月14日親の会社を継ぐメリットやデメリットとは?引き継ぐポイントなど
- 2025年3月7日企業価値を高める5つの方法|メリットや評価方法なども解説
- 2025年2月14日事業承継対策の方法とは|必要性や流れ、成功のポイントなど
- 2024年12月6日事業承継は弁護士へ相談すべき?役割や費用相場、選び方など
- 2024年11月22日事業承継のマッチング支援とは?利用するメリット・デメリットなど
- 2024年11月1日事業承継と廃業はどちらを選ぶべき?それぞれのメリット・デメリットなど
- 2024年10月25日経営承継円滑化法とは?事業承継で活用できる支援制度をわかりやすく解説
- 2024年10月11日事業承継における11の失敗事例|原因や成功させるポイントを詳しく解説
- 2024年9月20日事業譲渡における従業員への影響|退職金の扱いや注意点などを詳しく解説
- 2024年7月5日事業承継ガイドラインとは?概要や策定の背景をわかりやすく解説
- 2024年6月14日農業を事業承継するには?方法や成功に導くためのポイントを解説
- 2024年6月7日事業承継の計画について|策定の手順・ポイントや計画書の書き方
- 2024年5月31日事業承継における中小企業の現状や課題は?解決策とともに弁護士が解説
- 2024年5月24日事業承継のための融資「事業承継ローン」の種類や利用の流れについて
- 2024年5月2日相続対策としての事業承継|事業承継税制などの相続税対策も解説
カテゴリー一覧
タグ