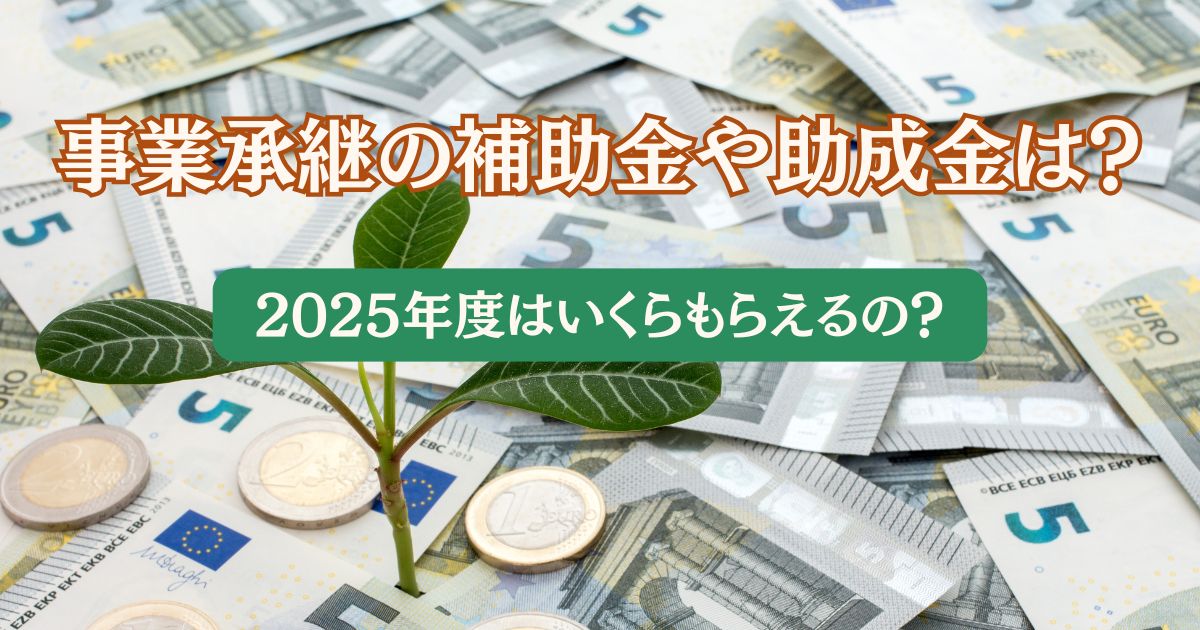事業承継を前向きに進めたいけれど、事業承継に使える補助金・助成金が「結局どれだけあるのか」「自社は対象なのか」がわからず、検討を進めづらい状況ではないでしょうか。
実は事業承継の現場では、設備更新や専門家費用、廃業・再チャレンジまで幅広く支援される補助金・助成金が存在します。。
とはいえ、「いくらもらえるの?」「対象経費は何?」という疑問が沸くのも当然です。
本記事では、制度の全体像を整理し、2025年度の上限額や対象者・対象経費、返済の要否などについて解説します。

目次
この記事を監修した弁護士
西田 幸広 法律事務所Si-Law代表
弁護士・法律事務所Si-Law/(株)TORUTE代表・西田幸広 熊本県を中心に企業顧問70社、月間取扱160件以上(2025年8月時点)。登録3,600社・20超業種を支援し、M&A・事業承継を強みとする。弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士の資格保有。YouTubeやメルマガで実務解説・監修/寄稿多数。LINE登録特典で「事業承継まるわかりマニュアル」提供。
事業承継の補助金や助成金はどんなものがある?
事業承継の補助金や助成金は、事業の引き継ぎや経営革新を目的として、国や地方自治体でいくつか用意されています。
そのなかでも、国策的な柱となるのが「事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)」です。
目的に応じて以下の4枠に分かれ、承継の前後をサポートしてくれます。
- 事業承継促進枠(承継を契機におこなう設備投資・新分野展開など)
- 専門家活用枠(M&A仲介やFA・DD等の専門家費用)
- PMI推進枠(統合後の専門家活用・設備投資)
- 廃業・再チャレンジ枠(原状回復費や在庫処分等)
状況によっては併用可能で、賃上げをおこなう場合の上限引き上げなど政策連動の加点もあります。
まずは「どの段階の費用(専門家への報酬かM&A後の設備投資かなど)を補助してもらいたいか」検討するようにしましょう。
その目的を判断の基準として、対象となる枠(支援制度)を選ぶのが効率的です。
事業承継の補助金や助成金の目的とは
事業承継の補助金や助成金の目的には、以下のものがあります。
- 廃業を防ぎ経済の活力を維持すること
- 事業を守るだけでなく発展させること
- M&A(買収・合併)を円滑に進めること
- 廃業後の再チャレンジを支援すること
補助金のゴールは、「廃業を防ぎ、事業と雇用を地域に残す」ことです。
後継者不足や投資余力の乏しさで止まっていた更新・挑戦を、国が一部負担して背中を押します。
加えて、M&Aの専門家費用や合併・買収後のPMI(統合プロセス)まで対象とし、単なる「引き継ぐだけ」で終わらず、承継後の稼ぐ力を底上げする設計です。
さらに、やむを得ず廃業する局面でも関係者に迷惑をかけないよう原状回復や在庫廃棄を支援し、再チャレンジを後押しします。
結果として、地域の生産性向上と持続的な賃上げにつなげることが狙いです。
それぞれの目的について、さらに詳細に解説していきます。
廃業を防ぎ経済の活力を維持すること
日本の中小企業は、地域経済の屋台骨です。
にも関わらず、後継者難や投資遅れで「本当は続けられるのにたたんでしまう」廃業が生まれがちになっています。
そこで、承継にともなう設備投資や外注・委託、知財関連費などに補助を入れ、必要な更新・省力化・DX(デジタルトランスフォーメーション)を実行しやすくします。
その結果、雇用の安定や取引先の連鎖を守ることにつながり、地域全体の経済循環を維持できるようになるのです。
補助金は一時的な救済策ではなく、事業承継後の生産性向上を通じて、企業が自力で成長を続けられるように支援することを目的としています。
まずは自社の抱える更新課題を書き出し、「その課題解決に必要な費用が補助金の対象となる費目に当てはまるか」を確認することから始めてください。
事業を守るだけでなく発展させること
承継は、ゴールではなくスタートです。
補助金は既存事業を守るだけでなく、新商品開発・新市場開拓・工程の自動化・データ活用など、承継後の発展的な投資にも幅広く対応しています。
特に小規模事業者は補助率(最大3分の2)が優遇され、限られた自己資金でも発展投資を仕掛けやすくなっています。
承継の機会に設備更新×人材育成×デジタル活用をセットで計画すれば、次の10年に耐えうる強い収益構造の基盤をつくり出すことも可能です。。
金融機関・専門家と事業計画を擦り合わせ、その計画に必要な費用を補助金の対象となる経費に正確に落とし込むのがポイントです。
M&A(買収・合併)を円滑に進めること
事業承継の補助金は、親族内・従業員承継だけでなく、第三者承継(M&A)も活用可能です。
専門家活用枠では、登録済みのM&A支援機関による仲介やFA(フィナンシャルアドバイザー)費用・企業価値算定・デューデリジェンス(DD)・表明保証保険料などが対象です。
大型の買収で一定要件を満たす場合は、上限2,000万円も視野に入ります。
さらにPMI推進枠では、統合後の専門家活用や設備投資も支援してくれます。
買収前後を切れ目なく補助することで、現場負担を抑えて「いい承継・いい統合」の実現を目指します。
廃業後の再チャレンジを支援すること
すべての事業が承継できるわけではありません。
やむを得ず廃業を選ぶ場合も、在庫廃棄・解体・原状回復・リース解約などは費用負担が重い課題です。
廃業・再チャレンジ枠はこれらを対象とし、他枠との併用申請で上乗せも可能となります。
関係者への影響を最小化しつつ、経営者の次の挑戦を後押ししてくれます。
適切な手続きで廃業することも、地域経済にとっては重要となるからです。
早めに計画を立て、専門家や商工会議所と連携して進めるようにしてください。
2025年度は事業承継の補助金でいくらもらえる?

事業承継・M&A補助金は、2025年度(令和7年時点・令和6年度補正事業)では、以下のようになっています。
| 事業承継促進枠 | 上限800万円~1,000万円(賃上げ実施で1,000万円)補助率2分の1または3分の2(小規模は最大3分の2) |
| 専門家活用枠 | 【買い手支援】600万円~800万円(DD申請で+200万円、要件により2,000万円枠あり) 【売り手支援】600万円~800万円補助率は条件に応じ3分の1・2分の1・3分の2など |
| PMI推進枠 | 【専門家活用】上限150万円(2分の1) 【事業統合投資】800万円~1,000万円(賃上げで1,000万円、補助率2分の1または3分の2) |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 上限150万円で他枠に加算併用可能 |
こちらは改正が入る場合もあるため、常に最新の情報を確認するようにしてください。
補助金や助成金は返さなくていい?
結論、補助金や助成金は原則返済不要です。
ただし「採択が決定した=すぐに入金される」わけではない点に注意が必要です。
補助金は、事業が完了した後におこなわれる実績報告と検査によって、費用が適正だと認められた金額のみが支払われます。
もし要件に不備があったり費用の証拠(エビデンス)が不足していたりすると、減額されたり、まったく支払われない(不交付)リスクもあります。
さらに、虚偽申請や目的外使用などの不正受給が判明した場合は、交付決定の取消し・全額返還(加算金付き)・事業者名の公表など、厳しい措置の対象となります。
補助金や助成金を申請する際は、適正な手続きの遵守、証拠書類(証憑)の厳格な管理、そして相見積もりの整備を徹底しておこなってください。

事業承継・M&A補助金の対象者は?
事業承継・M&A補助金は、中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)が対象です。
親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)のどの方法で事業を引き継ぐ場合にも対応しています。、
補助率や上限額は、事業の実態や賃上げの取り組み、あるいは赤字・利益率低下といった特定の条件を満たすかどうかで変わり、頑張っている企業ほど支援が手厚くなる仕組みです。
なお、個人事業主は青色申告が必須など、公募要領の細かな要件を満たす必要があります。
ここでは、以下の枠組みに合わせてさらに細かく対象について解説します。
- 事業承継促進枠(経営革新枠)
- 専門家活用枠
- PMI推進枠
- 廃業・再チャレンジ枠
申請の際は、会社のタイプ・承継の方法・財務状況という3つの要素を検討し、それに合致する支援の枠を選ぶようにしてください。
事業承継促進枠(経営革新枠)
事業承継促進枠(旧:経営革新枠)は事業承継を機に、新たな分野への展開や業態転換、設備更新などで生産性向上を目指す事業者を主な対象としています。
特に親族内承継や従業員承継を予定しているケースと相性が抜群です。
機械設備の入れ替え・工程の自動化・品質検査の省人化・データ活用による業務効率化といった、後継者が主導する「攻めの第一歩」の予算化に最適です。
さらに、賃上げの方針を計画に組み込むと、補助金の上限額引き上げという大きな恩恵も狙えます。
後継者が新しい体制づくりを主導し、将来に向けた発展投資を仕掛けるタイミングで、最も使い勝手が良い制度と言えます。
専門家活用枠
専門家活用枠は、M&A取引の成立前に発生する外部専門家への費用を補助するための枠です。
具体的には、M&Aの仲介・FA(ファイナンシャル・アドバイザー)費用、企業価値算定(バリュエーション)、デューデリジェンス(DD:買収監査)、セカンドオピニオンのほか、表明保証保険料なども対象となります。
買い手は、要件を満たせば上限2,000万円の補助も視野に入り、規模の大きい承継にも対応しやすくなります。
売り手側は赤字や利益率低下といった特定の財務状況にある場合、補助率が手厚くなる設計になっていて、売却コストの負担を軽減できます。
PMI推進枠
PMI推進枠は、M&Aの成約後に必要な統合作業(PMI:Post Merger Integration)を支援するための制度です。
専門家によるサポートや、事業統合にともなう様々な投資を後押ししてくれます。
組織や人事制度の統合・業務プロセス再設計・システムや会計基盤の統合・ブランディングや販路再編・人材育成まで、組織を一つにする「実装段階」で発生する費用が支援対象となります。
M&Aは契約の締結がゴールではなく、買収後に現場に新しい運営設計を根付かせられるかが本当の勝負です。
この枠を最大限に活かすには、統合の全体計画(ロードマップ)を立てた上で、離職率・原価率・相乗効果の金額など、効果を測るための具体的な目標(KPI)を明確に設定しましょう。
廃業・再チャレンジ枠
廃業・再チャレンジ枠は、事業の継続が難しく、やむを得ず廃業を選択する場合に、その後始末にかかる費用を支援する枠です。
具体的には、在庫の廃棄費用・建物の解体費用・テナントの原状回復費用・リース契約の解約費用などを補助してくれます。
この枠の目的は、他の補助金枠と併用して支援額を上乗せし、関係者(従業員や取引先)への影響を最小限に抑えることです。
これにより、経営者が費用負担の不安なく次の挑戦へとスムーズに踏み出せるよう、スタートラインを整備します。
個人事業主の場合
事業承継・M&A補助金は、個人事業主も申請可能です。
ただし、青色申告をしていることが前提となります。
補助金を申請するには、事業を引き継ぐ側(承継者)と引き継がれる側(被承継者)の両方が「中小企業者等」の定義を満たしていることが必須条件となります。
また、確定申告書Bや青色申告決算書の控えといった、必要書類の提出も求められます。
特に「創業支援類型」で申請する場合、申請時点ではまだ個人事業の開業や法人の設立前でも大丈夫です。
しかし、補助事業の期間内に必ず個人開業届(青色申告の承認)または法人設立を完了させる必要がある点に注意してください。
申請資格を満たしているかの最終確認は、最新の公募要領・FAQ(よくある質問)で必ず確認するようにしてください。
参考:中小企業庁|中小企業生産性革命推進事業「事業承継・M&A補助金」
事業承継・M&A補助金の対象経費は?

補助金の対象となる費用は、申請する「枠」ごとに細かく定められており、契約・発注・支払いなどの時期や証拠書類の要件が厳格です。
代表的な経費には、設備費・知的財産関連の費用・専門家への謝金や旅費・外注費や委託費・システム利用料・保険料・廃業費用(在庫廃棄、解体、原状回復、リース解約など)が挙げられます。
注意が必要な点は、「実績報告の際に証拠書類で裏付けられない費用は、一切支払われない(不交付になる)」ということです。
補助金申請が決まったら、見積もり・仕様書・納品確認(検収)の記録・支払い記録といったすべての書類を、「採択後に提出するためのもの」だと最初から意識して、厳密に整えておくことです。
対象者同様、こちらも枠組みに合わせて解説します。
事業承継促進枠(経営革新枠)
事業承継促進枠は、事業承継をきっかけとしておこなう新分野への進出・業態の変更・設備更新による省人化に必要な費用が対象となります。
具体的には、以下のような産業財産権関連の支出が中心です。
- 工作機械や工程自動化装置
- 検査・計測機器
- IoTセンサーといった設備の導入・入替
- 生産や品質管理ソフトやクラウドの初期設定・開発等のシステム整備
- 試作・設計・実装などの外注・委託
- 特許・商標の出願
- 先行技術調査 など
補助金を受けるには、KPI(生産性・原価・歩留まり・リードタイムなどの具体的な目標)や賃上げ方針が作成する事業計画と一致していることが重視されます。
一方で、汎用PCのみの購入や土地・建物の取得、過度な広告・交際費などは対象外となる傾向があるため注意が必要です。
専門家活用枠
専門家活用枠は、第三者承継(M&A)にともなう取引成立前に外部専門家に支払う費用が対象です。
主に以下の費用が補助の対象となりますが、「登録済みのM&A支援機関」によるサポートであることが条件です。
- 仲介手数料やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)手数料
- 企業価値算定
- 財務・法務・ビジネスに関するデューデリジェンス(DD:買収監査)
- セカンドオピニオン(他の専門家への相談費用)
- 表明保証保険(RWI)の保険料
これらの費用は、着手金・基本合意時報酬・成功報酬など、料金区分ごとに算定根拠を明確に提示することが求められます。
見積の相見積可否・契約形式・支払主体と支払時期の整合・議事録や稟議書類を含む証憑一式の整備を、計画の初期段階から厳格におこなうようにしてください。
PMI推進枠
PMI推進枠は、M&Aが成立した後(クロージング後)に、企業統合を成功させるために必要な費用が対象です。
統合を「実行」する段階で発生する、以下のような費用を幅広く支援します。
- PMI専門家の謝金・旅費や外部PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の伴走支援
- 業務プロセスの再設計
- 就業規則や評価制度を含む人事制度統合
- 会計・販売管理など基幹システムの統合・データ移行
- ブランド・販路統合にともなう必要最小限の制作・周知
- 人材育成・研修の外注費
補助金の費用は、作成した統合ロードマップと、具体的な達成目標(KPI)に明確に結びついていることが大前提となります。
例えば、統合による相乗効果額・原価率の改善・離職率の低下・在庫回転率の向上といった指標に紐づけることが必要です。
一方で、単なるウェブサイトのデザイン刷新や、日常的な広告・広報の支出は対象外となる傾向が強いため、補助金を使って何をおこなうかについては十分に注意してください。
廃業・再チャレンジ枠
廃業・再チャレンジ枠は、やむを得ず廃業する場合に必要な後始末の費用を支援します。
代表的には、以下のような内容です。
- 在庫の廃棄
- 設備・什器の撤去や解体
- 原状回復
- 産廃処分
- リース契約の解約費用 など
他の補助金枠と併用する計画では、移転・移設費が対象となるケースもあります。
不交付を避けるには、着手前の徹底した準備と時系列の厳守が重要です。
作業を始める前に、必ず工程表と証憑のチェックリストを用意し、現場写真・証明書・請求書・支払記録といったすべての証拠を漏れなく収集してください。
また、費用は補助対象期間内に「契約 → 発注 → 検収(納品確認) → 支払」という発生順序を厳密に守ることが、精算をクリアする鍵となります。
どの補助金枠を利用する場合でも、対象期間外の契約や支払いは原則として認められません。
そのため、スケジュールと社内稟議(承認プロセス)を前倒しで進め、すべての手続きの時系列に矛盾がないよう整合性をとることが重要です。
相見積もり・仕様書・議事録といった根拠資料は、後から探すことにならないよう、手続きと同時並行で保存するようにしましょう。
また、車両や土地建物の取得・汎用的なPC単体の購入・過度な広告や交際費・保守サービスのみの長期契約など、対象外になりやすい費目を事前に確認し、計画から排除しておく必要があります。
公募回ごとに細かなルールが改定されるため、申請前には必ず最新の公募要領・FAQで最終確認をおこなうようにしてください。
その他にも関連して使える補助金や助成金はある?
事業承継そのものを支える補助金とは別に、一般系の補助金制度も、投資の目的に合わせて活用可能です。
例えば、新分野展開や業態転換など大胆な投資には「事業再構築補助金」が使えます。
参考:事業再構築補助金
「ものづくり補助金」は、工程自動化や品質向上の設備導入など、生産性向上を目的とした投資に活用可能です。
また「小規模事業者持続化補助金」は、販路開拓や広告物・店舗改装など、営業力強化に焦点を当てた投資に使えます。
「IT導入補助金」は、会計・在庫・顧客管理(CRM)などのSaaS(クラウドサービス)導入にかかる費用に有効です。
参考:小規模事業者持続化補助金
参考:IT導入補助金2025
複数の補助金に申請する場合、同じ費用を二重に計上すること(重複計上)は禁止されています。
そのため、それぞれの補助金で対象とする経費と期間を明確に分け、費用の発生順序と進捗状況を管理するようにしましょう。
その他の税制や金融支援はある?
補助金に加え、税制・金融を組み合わせると資金計画が安定します。
事業承継税制(法人版特例)は、要件充足で株式の贈与・相続時の納税を猶予・免除でき、適用期限は2027年12月31日です。
事業承継計画の策定や認定を前倒しでおこない、その上で補助金による投資計画と実行の時系列をぴったりと合わせることが重要になります。
資金調達については、補助金に加えて日本政策金融公庫(JFC)が提供する事業承継・集約・活性化支援資金や、資本性ローンといった融資が有力な選択肢です。
徹底した資金管理によって、資金不足を防ぎ、計画的な成長投資を確実に実行できるはずです。
参考:日本政策金融公庫(JFC)|事業承継・集約・活性化支援資金
参考:日本政策金融公庫(JFC)|挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)
以下も記事でも、事業承継に使える補助金についてまとめています。
関連記事:事業承継に使える補助金は?2025年度のスケジュールや申請方法・対象経費なども解説!
TORUTE株式会社では、補助金や助成金のサポートもおこなっておりますので、ぜひご相談ください。

まとめ
この記事では、事業承継の補助金や助成金について解説しました。
2025年度の補助金制度は、事業承継の準備からM&A費用、統合(PMI)、そして廃業費まで、各フェーズを幅広く支援するよう整備されています。
原則として返済不要であり、個人事業主も対象です。
この支援額は、賃上げや業績などの条件で変動します。
ただし、事業完了後の実績報告と検査で適正と認められた分のみの支払いとなり、要件不備や不正は返還・不交付のリスクがあるため、ルールは非常に厳格です。
最新の公募要領を必ず確認し、税制や公庫融資といった他の制度と組み合わせながら、専門家と連携して計画を進めるようにしてください。

まずはお気軽にご連絡ください
受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)
事務所概要
熊本
熊本市東区桜木3-1-30 ヴィラSAWADA NO.6 102号室
福岡
福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F
コラム一覧
- 2026年1月14日熊本で事業承継をお考えの方!支援制度や補助金・相談先と進め方までを専門家がわかりやすく解説!
- 2026年1月14日事業承継特別保証制度とは?メリット・デメリットや要件・申請方法もまとめて紹介!
- 2026年1月7日事業承継で専門家が必要な理由は?選び方やタイミング・補助金は使えるのかも解説!
- 2026年1月7日事業承継の株式譲渡の方法は?メリットや手続き方法・税金の特例制度についても解説!
- 2025年12月31日事業承継の株価対策とは?3つの評価方式や自社株の引き下げ対策をまとめて解説!
- 2025年12月31日承継会社とは?分割会社との違いや手続き方法・メリットとデメリットもわかりやすく解説!
- 2025年12月24日事業承継補助金の対象経費は?枠組みごとのルールや金額・認められない例も紹介!
- 2025年12月24日事業承継税制の延長はいつまで?提出期限のスケジュールや緩和要件についても解説!
- 2025年12月17日事業承継補助金は親子間でも対象?要件や申請方法・利用するときの難易度も解説!
- 2025年12月17日事業承継の手順は?引き継ぐ3つの要素や必要書類・受けられるサポートもまとめて紹介!
- 2025年12月10日事業承継と相続との違いは?税制の対象や手続き方法・起こりやすいリスクも紹介!
- 2025年12月10日事業承継の税制優遇とは?制度の内容や期限・使えないケースについても徹底解説!
- 2025年11月27日事業承継の費用の相場はどれくらい?税金対策や補助金・誰が負担するのかも解説!
- 2025年11月27日事業承継と会社売却の違いは?メリット・デメリットや従業員はどうなるのかも徹底解説!
- 2025年11月27日事業承継後のトラブルで起こりやすい事例は?原因や対応策・成功例までまとめて紹介!
- 2025年11月27日事業承継の相談先10選を紹介!相談費用は無料なのか・選び方のポイントも解説!
- 2025年11月26日事業承継の企業価値とは?算出方法や3つのアプローチ・高値がつくケースも解説!
- 2025年11月26日事業承継の後継者不足の原因は?担い手がいない理由や解決策・成功例まで紹介!
- 2025年11月26日中小企業の事業承継問題とは?課題や問題点・具体例についてもわかりやすく紹介!
- 2025年11月25日事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!
- 2025年11月25日事業承継の補助金や助成金は?2025年度はいくらもらえるのか・対象経費も解説!
- 2025年11月25日事業承継の手続きで法人の場合の流れは?必要書類や税金などの費用・補助金もまとめて解説!
- 2025年11月24日事業承継に使える補助金は?2025年度のスケジュールや申請方法・対象経費なども解説!
- 2025年11月24日事業承継でやるべきことリストを紹介!必要な知識や書類・課題についても解説!
- 2025年11月24日事業承継ファンドとは?活用が有効なケースやメリット・デメリットも紹介!
- 2025年11月23日事業承継税制の要件とは?特例措置と一般措置の違いやメリット・デメリットも解説
- 2025年11月23日事業承継とM&Aの違いは?メリットとデメリットや選び方のポイント・課題も徹底解説!
- 2025年11月23日事業承継とは?基本的な考え方や支援制度・手順までをわかりやすく徹底解説!
- 2025年3月14日親の会社を継ぐメリットやデメリットとは?引き継ぐポイントなど
- 2025年3月7日企業価値を高める5つの方法|メリットや評価方法なども解説
- 2025年2月14日事業承継対策の方法とは|必要性や流れ、成功のポイントなど
- 2024年12月6日事業承継は弁護士へ相談すべき?役割や費用相場、選び方など
- 2024年11月22日事業承継のマッチング支援とは?利用するメリット・デメリットなど
- 2024年11月1日事業承継と廃業はどちらを選ぶべき?それぞれのメリット・デメリットなど
- 2024年10月25日経営承継円滑化法とは?事業承継で活用できる支援制度をわかりやすく解説
- 2024年10月11日事業承継における11の失敗事例|原因や成功させるポイントを詳しく解説
- 2024年9月20日事業譲渡における従業員への影響|退職金の扱いや注意点などを詳しく解説
- 2024年7月5日事業承継ガイドラインとは?概要や策定の背景をわかりやすく解説
- 2024年6月14日農業を事業承継するには?方法や成功に導くためのポイントを解説
- 2024年6月7日事業承継の計画について|策定の手順・ポイントや計画書の書き方
- 2024年5月31日事業承継における中小企業の現状や課題は?解決策とともに弁護士が解説
- 2024年5月24日事業承継のための融資「事業承継ローン」の種類や利用の流れについて
- 2024年5月2日相続対策としての事業承継|事業承継税制などの相続税対策も解説
カテゴリー一覧
タグ