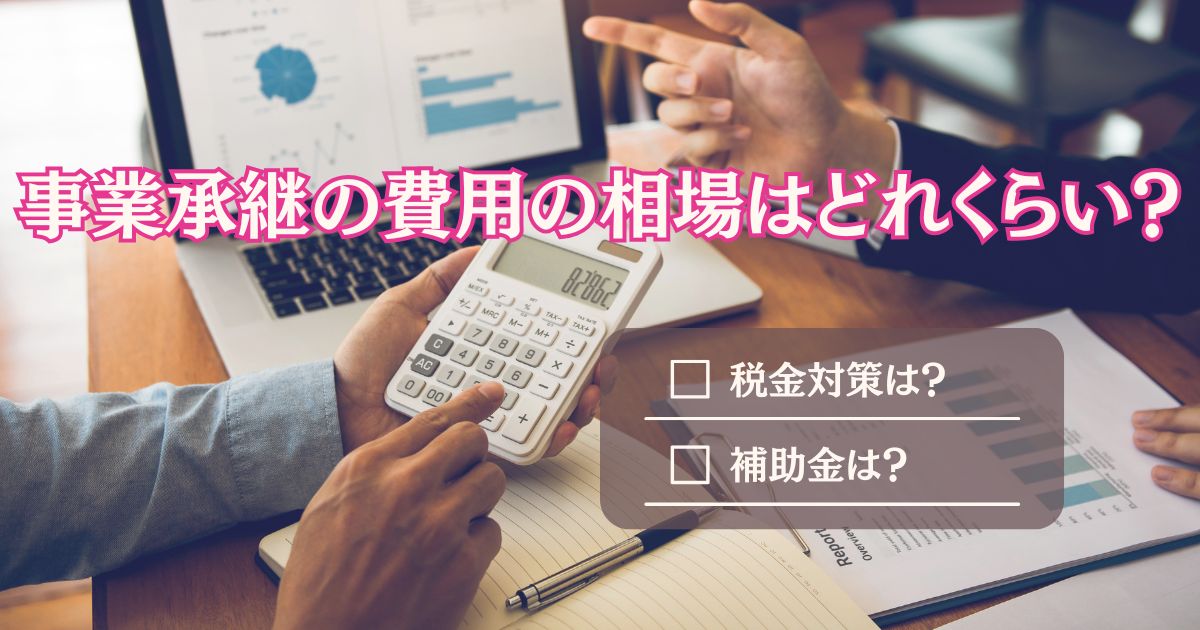事業承継を進める上で、費用の相場を把握しておかないことには、不安も大きいのではないでしょうか。
実際の負担は税金や専門家への報酬に加え、さまざまな手続きの費用が積み上がることで決まります。
あわせて「誰が費用を負担するのか」「税金対策や補助金でどこまで軽減できるのか」も早い段階で確認しておくのがおすすめです。
そこで本記事では、事業承継にかかる費用相場や税金対策、補助金などを詳しく解説します。
条件に沿った概算の当て方がわかり、見積もりの抜けを減らせるはずなので、参考にしてください。

目次
この記事を監修した弁護士
西田 幸広 法律事務所Si-Law代表
弁護士・法律事務所Si-Law/(株)TORUTE代表・西田幸広 熊本県を中心に企業顧問70社、月間取扱160件以上(2025年8月時点)。登録3,600社・20超業種を支援し、M&A・事業承継を強みとする。弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士の資格保有。YouTubeやメルマガで実務解説・監修/寄稿多数。LINE登録特典で「事業承継まるわかりマニュアル」提供。
事業承継にかかる費用について
事業承継にかかる費用は、主に次の3つに分類できます。
- 税金
- 専門家への報酬
- その他の費用
まず税金は、相続・贈与・登記・不動産の名義変更などにともなって発生し、どの税金がかかるかは引き継ぎの方法によって異なります。
次に専門家への報酬ですが、依頼する内容や作業の難しさによって金額が変わるため、あらかじめ見積もりを確認しておくことが大切です。
またその他の費用としては、会社の資産や契約内容を整理するための調査費用・許可や登記の手続き費用・金融機関との調整にかかる費用などがあります。
これらの費用は一つひとつの積み重ねで決まるため、何にどれくらいかかるのかを整理しておくとよいでしょう。
詳細や相場の目安について、後ほど詳しくご紹介します。
承継手数料とは?
「承継手数料」とは、会社を第三者に引き継ぐときに、仲介会社などへ支払う成功報酬などの費用のことです。
一般的には、取引金額に応じて手数料の割合が変わる「段階制」で計算されます。
具体的には、取引金額が大きくなるほど手数料の割合は少しずつ下がっていく、といった仕組みです。
契約の内容によっては、成功報酬の他にも最初に払う着手金や、途中で支払う中間金などが発生する場合もあります。
大切なのは「どの金額を基準に計算するのか・どこまでを仲介会社が担当するのか」を契約書で明確にしておくことです。
契約前には、手数料の計算方法・支払い時期・担当者の体制を一覧で確認し、複数の会社を比較して納得のいく条件を選ぶようにしましょう。
事業承継の費用は誰が負担するの?
事業承継にかかる費用は、どの方法で引き継ぐかや契約内容によって大きく変わります。
| 承継方法 | 税金 | 専門家報酬 | 登記費用 |
|---|---|---|---|
| 親族内承継 | 後継者 | 会社または現経営者 | 会社 |
| 従業員承継 | 後継者 | 会社または現経営者 | 会社 |
| M&A(第三者承継) | 取引条件による | 各自のアドバイザー費用を各自負担 | 契約で取り決める |
親族や従業員に引き継ぐ場合は、相続税や贈与税といった税金を後継者が負担することが多くみられます。
一方で、会社の資産評価・登記・専門家への報酬などは、会社が支払うケースが一般的です。
なお、親族間であっても「株式や事業の売買」という形で承継をおこなう場合があり、その際は契約条件に応じて費用分担を決めることになります。
第三者に売却するM&Aの場合は、売り手と買い手がそれぞれ自分の専門家費用を負担するのが基本となっています。
こうした費用の分担は曖昧にしておくと、後で「言った・言わない」のトラブルになりかねません。
契約書の中で「誰がどの費用を負担するか」をはっきり決め、支払い時期や金額の基準も一覧で確認しておくと安心でしょう。
事業承継の費用の相場はどれくらい?

事業承継にかかる費用には「これが正解」という決まった相場はありません。
会社の規模・資産の内容・どのように引き継ぐか・許可が必要な業種かどうかなどによって、大きく金額が変わります。
まずは全体を次の3つに分けて考えると、整理しやすくなるでしょう。
- 税金:相続税・贈与税・譲渡税・登記費用・不動産取得税など
- 専門家への報酬:会社の評価・契約・交渉・引き継ぎ計画に関わる費用
- その他の費用:印紙代・各種届出・人事やITなどの整備費用
どんな費用がいつ発生するのかをあらかじめ書き出して整理しておくと、抜け漏れを防ぎ、全体の資金計画も立てやすくなります。
ここからは、それぞれの項目について具体的に解説していきます。
税金
税金は、選ぶ承継方法によって種類も計算の仕方も変わります。
- 相続税
- 贈与税
- 法人税
- 消費税
- 登録免許税
- 不動産取得税
税金の金額そのものは、国の制度や法律によって決まりますが、会社の評価方法や取引の進め方によって実際の負担額が大きく変わることがあります。
そのため、どんな税金がかかるのか・どの場面で注意すべきなのかを、ひとつずつ整理して理解しておくことが大切です。
相続税
親族内承継で相続が発生した場合、会社の株や事業に使っている土地・建物などは相続財産として扱われ、相続税の対象です。
中小企業向けには「事業承継税制(特例)」という制度があり、一定の条件を満たせば税金の支払いを先延ばしにでき、将来的に免除される可能性もあります。
ただしこの制度を使うには、国への計画書の提出・雇用の維持・毎年の報告などが必要で、手続きを怠ると適用が取り消されることもあります。
そのため、早めに株の評価や相続のタイミングを整理し、必要書類や期限を一覧にしておきましょう。
贈与税
先代から後継者へ、会社の株や事業に使う資産を無償で引き継ぐと、贈与税の対象になります。
ただし、2025年10月現在では年間110万円までは非課税なので、その範囲内であれば税金はかかりません。
また、中小企業向けの事業承継税制(特例)を使えば、一定の条件を満たすことで税金の支払いを猶予または免除してもらえる場合もあります。
生前に少しずつ株を渡す方法も有効ですが、国への計画書の提出・認定機関の関与・事業を続けることなどの条件をきちんと守らなければなりません。
また、一度に渡すか・段階的に進めるか・家族への配慮をどう組み込むかを早めに話し合っておくと安心でしょう。
丁寧に計画して進めることが、税金のトラブルを防ぎ、家族みんなが納得できる承継につながるはずです。
法人税
会社の株を売って事業を引き継ぐ場合、売った側が法人であれば、その利益には法人税がかかります。
これは売却で得たお金が、会社の「利益」とみなされるためです。
ただし、実際にかかる税金は法人税だけでなく、地方税なども含めた合計額(実際の負担率)で考える必要があります。
また、過去の赤字の繰越分があるかどうか・グループ会社との関係・決算時期や配当の方針によっても、結果が大きく変わることが考えられます。
どの方法で進めるかを決める前に、いくつかのパターンで税金や手取り金額を比較しておくと安心でしょう。
簡単な比較表を作り、税金の額や入金の時期を見える化しておくと、後で迷わず判断できるはずです。
消費税
事業をまるごと引き継ぐ「事業譲渡」の場合、売るものの内容によって消費税がかかるものとかからないものがあります。
たとえば、機械・備品・営業権(のれん)には消費税がかかりますが、土地や株などは消費税の対象外です。
すべてをまとめて売買する場合でも、どの資産が課税対象で、どれが非課税なのかをはっきり分けておくことが大切になるでしょう。
この区別が曖昧だと、あとで税金の処理や買い手との認識が食い違うおそれがあります。
また税込か税抜かによって、最終的に手元に残る金額も変わるため、消費税をどちらが負担するのかも契約書で明確にしておきましょう。
さらにインボイス制度への対応状況も確認し、あらかじめ消費税分の資金を確保しておくと、取引後に思わぬ出費が発生するリスクを防げます。
登録免許税
事業承継の際には、社長の交代・本店の移転・会社の合併や分割などにともなって「登記」の手続きが必要になります。
このときにかかるのが、登録免許税です。
税金の金額は手続きの内容によって異なり、あらかじめ決まっているものもあれば、資本金の大きさによって変わるものもあります。
1件ごとの金額は大きくなくても、複数の登記をまとめておこなうと合計が思ったより高くなることもあるでしょう。
そのため、どんな登記がいつ必要になるかを早めに整理しておくことが大切です。
不動産取得税
工場・倉庫・事務所などの不動産を購入したり引き継いだりすると、不動産取得税という税金がかかります。
これは都道府県に納める税金で、土地や建物の評価額をもとに計算されます。
ただし土地の広さや用途によっては、税金が軽くなる特例が使える場合もあるでしょう。
そのため、まずは固定資産の評価額を確認し、いつ・どんな目的で不動産を取得するかを整理しておくことが大切です。
また、登記にかかる登録免許税や修繕・改装費なども合わせて考えておくと、全体の資金計画が立てやすくなります。
建物の用途変更や再編をする場合は、都市計画上の制限や手続きも事前に確認しておきましょう。
わからない点は専門家に相談し、判断の理由を記録に残しておくと安心です。
専門家への報酬
専門家への報酬は、どこまで依頼するかによって大きく変わります。
まずは会社の現状を整理し、株価(会社の価値)を確認することから始めるとよいでしょう。
その上で必要に応じて、財務・税金・法律・人事・ITなどの調査や、契約書づくり・許認可の確認・統合の準備(PMI)といったサポートを追加で依頼する形になります。
特にM&A(第三者承継)では、着手金・中間金・成功報酬・最低手数料の有無や、報酬を「売却金額」か「会社全体の価値」のどちらで計算するのかを、事前に確認しておくことが大切です。
依頼先を選ぶときは、費用の仕組み・支払い時期・担当体制を一覧にまとめ、複数社を比較して検討しましょう。
税理士・公認会計士
税理士や公認会計士は、会社の価値を評価したり、税金の扱いを整理したりする専門家です。
事業承継では、株価の計算・税金の確認・事業承継税制の申請や管理・将来の資金計画づくりなど、幅広いサポートをおこないます。
例えば事業譲渡の場合は、どの部分に消費税がかかるかを正確に分ける必要があります。
また、株式を譲渡する場合は、利益にかかる税金や特例制度の扱いを慎重に確認しておくことが大切になるでしょう。
依頼する際は、評価・申告・申請など「どこまでの作業をお願いするのか」をはっきり決め、将来の売上見通しや業界データなど「計算の前提条件」を共有しておくと、後で食い違いが起こりにくくなるはずです。
弁護士
弁護士は、事業承継やM&Aの契約を安全に進めるための専門家です。
契約内容が法律に合っているかを確認し、契約書の作成や交渉、万が一のトラブルを防ぐための条文づくりなどを担当します。
例えば、契約後に同じ業界で競合する行為を防ぐ取り決めや、引き継ぐ資産や情報に問題がないと約束する内容など、細かい部分まで確認する役割があります。
交渉が複雑になるほど時間と費用が増えるため、あらかじめ「譲れない条件」と「代わりに提案できる案」を整理しておくとスムーズに進められるでしょう。
また、契約を結んで終わりではなく、契約後の運用(PMI)までを見据えた内容にしておくことが重要です。
「契約はできたけれど、実際の運用で困った」という事態を防ぐためにも、現実的で実行しやすい契約にすることを意識しておきましょう。
M&A仲介会社
M&Aの仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)は、会社を引き継ぐ相手を探したり、条件を調整したり、契約の最終段階までサポートする専門家です。
どの会社に依頼するかで費用が大きく変わるため、報酬の仕組みをよく確認しておくことが大切になるでしょう。
報酬は多くの場合、「レーマン方式」と呼ばれる成功報酬の仕組みが使われます。
これは、取引金額に料率(%)を掛けて報酬を計算する方法で、最低手数料の有無や「売却金額」なのか「会社全体の価値」なのかによって最終金額が変わります。
契約を結ぶ前に、広告や営業のやり方が適切か・買い手と売り手の両方を担当していないか・重要な説明が十分におこなわれているかをしっかり確認しておきましょう。
また、費用の安さだけで判断せず、資料のわかりやすさ・買い手の選定力・引き継ぎ後のサポートの丁寧さといった対応の質まで見ることが大切です。
その他の費用
事業承継では、税金や専門家の費用以外にも、次のようなさまざまな実務的な費用がかかります。
- 会社の価値をまとめた「評価書」の作成費用
- 財務・税務・法律・人事・ITなどを専門家が調べる調査費用
- 許認可の引き継ぎや再取得の手続き費用
- 登記や印紙などの手続き費用
- 銀行など金融機関との契約変更費用
- 引き継ぎ後の準備費用(人事制度の見直しや会計・販売システムの切り替えなど)
また、見落としがちなのが、従業員・取引先・金融機関に対して説明をおこなうための資料作成や説明会の運営にかかる費用です。
これは「合意形成コスト」と呼ばれ、金額だけでなく引き継ぎのスピードやスムーズさにも影響します。
こうした費用を把握するためにも、早めに必要な作業を洗い出し、担当者と期限を決めておくようにしましょう。

事業承継・引継ぎ支援センターの料金は?
全国に設置されている事業承継・引継ぎ支援センターでは、初期相談を原則無料で受けられます。
現状の整理・方向性の確認・後継者候補とのマッチングの可能性を探るところまで、費用をかけずに相談できるのが大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、より踏み込んだ検討をおこなう段階では、税理士や弁護士などの専門家による調査やサポートが必要になることが多く、その部分から費用が発生する場合が多くなります。
つまり最初の相談は無料でも、実際に具体的な作業に入ると有料になる場合がある、ということを理解しておくと安心です。
利用する際は、まず無料相談で自社の課題や優先順位を整理し、必要に応じて有料サポートの内容や費用の見積もりを確認しておくと、全体の計画を立てやすくなるでしょう。
承継先の違いで費用は変わる?

事業承継にかかる費用は、「誰に会社を引き継ぐか」によって大きく変わります。
- 親族内承継の場合
- 従業員承継の場合
- M&A(第三者承継)の場合
どの方法を選ぶにしても、「費用の安さ」だけでなく、引き継ぎの確実さ・スピード・引き継ぎ後の安定性といった「質の面」からも全体のバランスを考えるようにしましょう。
親族内承継の場合
親族内承継で会社を引き継ぐ場合、主にかかる費用は、相続税・贈与税・株式の評価・登記の手続き費用などです。
比較的費用を抑えやすい承継方法で、家族の合意づくりと税金の仕組みを上手に活用することが大切と言えるでしょう。
税金の負担を減らすには、「事業承継税制」という国の制度を活用し、条件を満たせば一定の期間、税金の支払いを先延ばしにできる場合もあります。
また、家族間での話し合いや相続トラブルを防ぐための「遺留分(いりゅうぶん)」の調整に必要な資料づくりなどにも、別途費用がかかることが考えられます。
事業承継は一度で終わるものではなく、毎年の報告や書類の管理を続ける必要があるため、10年ほどの長い計画で考えておきましょう。
従業員承継の場合
従業員や役員に引き継ぐ従業員承継の場合は、法人税や所得税のほか、会社を買い取るための資金や契約書の作成・専門家への相談費用などがかかります。
また経営体制が変わることで、人事制度や給与の見直し、銀行や取引先への説明などにも費用が必要になることがあるでしょう。
外部の専門家に依頼する場合は、着手金や成功報酬などの料金体系、そしてどこまでの仕事を依頼できるのかを、契約前にしっかり確認しておくのがおすすめです。
さらに、社内の理解を得るために、従業員向けの説明会や話し合いの場を設ける費用や時間も忘れずに見込んでおくとよいでしょう。
こうした準備を丁寧に進めることで、引き継ぎ後の会社運営を安定させやすくなります。
M&A(第三者承継)の場合
M&A(第三者への承継)の場合は、所得税に加えて、仲介会社やアドバイザーに支払う手数料が主な費用になるでしょう。
他にも、会社の内容を詳しく調べるための専門家への調査費用や、契約交渉に関する費用などがかかります。
費用は取引の金額や契約内容によって大きく変わるため、報酬の計算方法や支払いの時期を事前にきちんと確認しておくことが大切です。
また、手数料の安さだけで判断せず、担当者の経験・対応の丁寧さ・引き継ぎ後のサポート体制なども重視して選ぶことで、安心できる取引と納得のいく承継につながりやすくなります。
事業承継にかかる税金の対策はできる?

事業承継における費用対策は、十分に可能です。
主に以下の4つが、対策の柱になると考えます。
- 事業承継税制の活用
- 株価の引き下げ対策
- 生前贈与の活用
- 生命保険の活用
どの方法を選ぶ場合でも、期限を守り、必要な書類や条件をきちんと管理することが成功の分かれ道になります。
まずは国や自治体が公表している公式情報を確認し、今の制度に沿って計画を立てるようにしましょう。
どの対策もそれだけで完璧というわけではないので、会社の状況に合わせて複数の方法を組み合わせることが大切です。
事業承継税制の活用
事業承継税制は、会社の株式を相続や贈与で引き継ぐときに使える国の支援制度です。
この制度を使うと、一定の条件を満たすことで相続税や贈与税の支払いを先延ばし(猶予)でき、将来的に免除されることもあります。
ただし、利用するには事前の申請・雇用の維持・毎年の報告など、いくつかの条件をきちんと守らなければなりません。
まずは制度を使えるかどうかを確認し、その上で必要な書類や関係者の役割分担を整理しておきましょう。
手続き後も、定期的に進み具合をチェックする仕組みを作っておくと安心です。
この制度は改正が多いため、最新の情報をこまめに確認し、必要に応じて専門家と一緒に書類や期限の管理を進めるのがよいでしょう。
参考:国税庁|事業承継税制特集
株価の引き下げ対策
株価は、税金の金額に直結する重要な大切なポイントと言えます。
そのため、まずは使っていない資産の整理や役員報酬・配当の見直しなど、会社の実態に合った形へ整えることが大切です。
また、税金の計算に使われる評価方法と内容が合っているかを確認し、数字の根拠や記録をきちんと残しておくようにしましょう。
数字だけを調整するような表面的な対策は、あとでトラブルのもとになりかねません。
税金を減らすためだけに不自然な株価操作をおこなうと、「租税回避」とみなされて違法または否認されるおそれがあります。
あくまでも会社の実情に即した正当な見直しが大切ですので、早めに専門家の意見を取り入れ、誰が見ても説明できる形で計画を立てるのがおすすめです。
さらに、状況の変化に合わせて定期的に見直しをおこなうことで、税金の負担を抑えながら安定した事業承継を進めやすくなるでしょう。
生前贈与の活用
生前贈与は、社長の立場や株式を少しずつ後継者に引き継ぐ方法で、条件を満たせば税金の支払いを先延ばしにできる制度を使えるケースもあります。
ただし、進め方を誤ると後から思わぬ税金が発生することがあるため注意が必要です。
例えば、「一度にまとめて贈与するか・何年かに分けて少しずつ贈与するか」などを、家族の状況や会社の実情に合わせて考えることが大切になるでしょう。
やり方に迷う場合は、早めに税理士などの専門家に相談し、計画や期限を一緒に整理しておくと安心です。
生命保険の活用
生命保険は、相続税や退職金、株の買い取り資金などを準備しておくために有効な方法と言えるでしょう。
あらかじめ計画的に加入しておくことで、いざという時に資金不足で困るリスクを減らすことができます。
ただし、保険に関する税金のルールはたびたび変わるため、誰が受け取るのか・どう処理するのか・どのくらいの保険料を支払うかを慎重に考える必要があります。
また、「節税のため」だけではなく、事業を安定して続けるためのリスク対策のひとつとして考えることが大切です。
契約の前に、将来の支払いと受け取りの時期を整理しておくと、後継者が安心して資金を管理できる体制を作りやすくなるでしょう。
最初にもお伝えしたとおり、会社の状況に合わせた設計が必要になるため、税金対策に悩む場合は、ぜひTORUTE株式会社にご相談ください。

事業承継に使える補助金は?
事業承継に使える補助金は、国や自治体が実施する「事業承継・引継ぎ補助金」が代表的と言えます。
これは、M&Aや事業承継にかかる専門家への費用・設備の購入・廃業や再スタートにかかる費用などの一部を支援してくれる制度です。
また、「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」といった制度もあり、設備投資や新しい商品の開発、販路の拡大などに使える場合もあります。
事業承継をきっかけに申請すると、特例的に加点や補助上限の引き上げを受けられる場合もあるでしょう。
どの補助金が合うかは、事業の内容や目的によって異なるため、事前に内容をしっかりと確認して選ぶことが大切です。
事業承継の補助金はいくらもらえる?
事業承継で利用できる補助金の支給額は、制度や目的によって異なります。
例えば「事業承継・引継ぎ補助金」では、M&Aや設備投資などにかかる費用の一部が支給され、最大で500万〜800万円ほどが上限となるケースが多いでしょう。
どのくらい負担してもらえるかは、おおむね2分の1〜3分の2程度が一般的です。
また、「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」といった制度では、50万円〜1,000万円程度の支援を受けられる場合もあります。
ただし、金額や条件は年度や募集内容によって変わるため、必ず最新の公募要領を確認し、早めに準備を始めておくことが大切です。
参考:事業承継・M&A補助金
参考:ものづくり補助金総合サイト
参考:小規模事業者持続化補助金
事業承継のご相談は「TORUTE株式会社」へ

事業承継は、法律・税金・資金・人の問題が複雑に関わる長期的なプロジェクトです。
判断が難しい場面も多く、費用の見通しも立てにくいため、専門家の客観的な支援が欠かせないと考えます。
TORUTE株式会社では、事業承継の方法選びから契約内容の整理、許認可や人事・知的財産の確認、引き継ぎ後の体制づくりまでを、経営者の立場に寄り添ってサポートさせていただいています。
「何から始めればよいかわからない」「この費用は妥当なのか知りたい」といった段階でも大丈夫です。
売上・資産・人員体制など、貴社の状況を踏まえ、おおよその費用感や優先すべきことを一緒に整理いたします。
必要に応じて、他の専門家とも連携し、過不足のない支援体制をご提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
経営の負担を増やさず、安心して事業を次の世代につなげる道筋を一緒に考えていきましょう。
\事業承継マニュアル無料プレゼント!/
まとめ
事業承継にかかる費用は、税金・専門家への報酬・実務にともなう経費の3つが中心であり、どれくらいの費用がかかるかは、承継の方法や会社の規模によって大きく変わります。
例えば、親族内の承継では相続税や贈与税が関係し、従業員承継では資金調達や人事の再整備が費用の中心になります。
第三者へのM&Aでは、仲介手数料や契約関連の費用が大きな割合を占めるでしょう。
また、税金を軽減できる制度や補助金を利用できるケースもあります。
これらの制度は内容が変わることもあるため、最新の情報を確認しておくことが大切です。
大事なのは「いくらかかるか」だけでなく、どんな費用が・いつ・どのくらい必要になるのかを把握することと言えるでしょう。
早めにしっかりと準備を積み重ねていくことで、安心して次の世代へ事業を引き継ぐことができるはずです。

まずはお気軽にご連絡ください
受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)
事務所概要
熊本
熊本市東区桜木3-1-30 ヴィラSAWADA NO.6 102号室
福岡
福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F
コラム一覧
- 2026年1月14日熊本で事業承継をお考えの方!支援制度や補助金・相談先と進め方までを専門家がわかりやすく解説!
- 2026年1月14日事業承継特別保証制度とは?メリット・デメリットや要件・申請方法もまとめて紹介!
- 2026年1月7日事業承継で専門家が必要な理由は?選び方やタイミング・補助金は使えるのかも解説!
- 2026年1月7日事業承継の株式譲渡の方法は?メリットや手続き方法・税金の特例制度についても解説!
- 2025年12月31日事業承継の株価対策とは?3つの評価方式や自社株の引き下げ対策をまとめて解説!
- 2025年12月31日承継会社とは?分割会社との違いや手続き方法・メリットとデメリットもわかりやすく解説!
- 2025年12月24日事業承継補助金の対象経費は?枠組みごとのルールや金額・認められない例も紹介!
- 2025年12月24日事業承継税制の延長はいつまで?提出期限のスケジュールや緩和要件についても解説!
- 2025年12月17日事業承継補助金は親子間でも対象?要件や申請方法・利用するときの難易度も解説!
- 2025年12月17日事業承継の手順は?引き継ぐ3つの要素や必要書類・受けられるサポートもまとめて紹介!
- 2025年12月10日事業承継と相続との違いは?税制の対象や手続き方法・起こりやすいリスクも紹介!
- 2025年12月10日事業承継の税制優遇とは?制度の内容や期限・使えないケースについても徹底解説!
- 2025年11月27日事業承継の費用の相場はどれくらい?税金対策や補助金・誰が負担するのかも解説!
- 2025年11月27日事業承継と会社売却の違いは?メリット・デメリットや従業員はどうなるのかも徹底解説!
- 2025年11月27日事業承継後のトラブルで起こりやすい事例は?原因や対応策・成功例までまとめて紹介!
- 2025年11月27日事業承継の相談先10選を紹介!相談費用は無料なのか・選び方のポイントも解説!
- 2025年11月26日事業承継の企業価値とは?算出方法や3つのアプローチ・高値がつくケースも解説!
- 2025年11月26日事業承継の後継者不足の原因は?担い手がいない理由や解決策・成功例まで紹介!
- 2025年11月26日中小企業の事業承継問題とは?課題や問題点・具体例についてもわかりやすく紹介!
- 2025年11月25日事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!
- 2025年11月25日事業承継の補助金や助成金は?2025年度はいくらもらえるのか・対象経費も解説!
- 2025年11月25日事業承継の手続きで法人の場合の流れは?必要書類や税金などの費用・補助金もまとめて解説!
- 2025年11月24日事業承継に使える補助金は?2025年度のスケジュールや申請方法・対象経費なども解説!
- 2025年11月24日事業承継でやるべきことリストを紹介!必要な知識や書類・課題についても解説!
- 2025年11月24日事業承継ファンドとは?活用が有効なケースやメリット・デメリットも紹介!
- 2025年11月23日事業承継税制の要件とは?特例措置と一般措置の違いやメリット・デメリットも解説
- 2025年11月23日事業承継とM&Aの違いは?メリットとデメリットや選び方のポイント・課題も徹底解説!
- 2025年11月23日事業承継とは?基本的な考え方や支援制度・手順までをわかりやすく徹底解説!
- 2025年3月14日親の会社を継ぐメリットやデメリットとは?引き継ぐポイントなど
- 2025年3月7日企業価値を高める5つの方法|メリットや評価方法なども解説
- 2025年2月14日事業承継対策の方法とは|必要性や流れ、成功のポイントなど
- 2024年12月6日事業承継は弁護士へ相談すべき?役割や費用相場、選び方など
- 2024年11月22日事業承継のマッチング支援とは?利用するメリット・デメリットなど
- 2024年11月1日事業承継と廃業はどちらを選ぶべき?それぞれのメリット・デメリットなど
- 2024年10月25日経営承継円滑化法とは?事業承継で活用できる支援制度をわかりやすく解説
- 2024年10月11日事業承継における11の失敗事例|原因や成功させるポイントを詳しく解説
- 2024年9月20日事業譲渡における従業員への影響|退職金の扱いや注意点などを詳しく解説
- 2024年7月5日事業承継ガイドラインとは?概要や策定の背景をわかりやすく解説
- 2024年6月14日農業を事業承継するには?方法や成功に導くためのポイントを解説
- 2024年6月7日事業承継の計画について|策定の手順・ポイントや計画書の書き方
- 2024年5月31日事業承継における中小企業の現状や課題は?解決策とともに弁護士が解説
- 2024年5月24日事業承継のための融資「事業承継ローン」の種類や利用の流れについて
- 2024年5月2日相続対策としての事業承継|事業承継税制などの相続税対策も解説
カテゴリー一覧
タグ