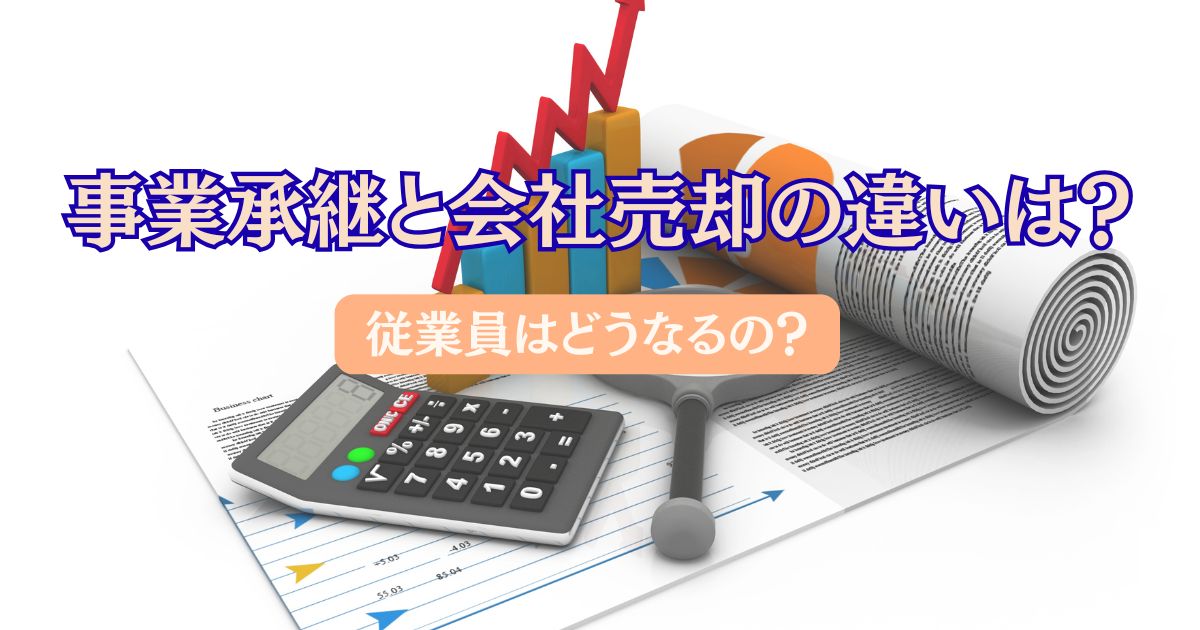事業承継と会社売却の違いが気になって、情報を探す方は多くいらっしゃいます。
ご自身の年齢・体調の変化・銀行の個人保証・従業員の将来などを思うと、どちらを選ぶべきか迷うのはごく自然なことです。
本記事では、事業承継と会社売却の基本・メリットとデメリット・従業員はどうなるのか・税金を差し引いた手残りの考え方までを徹底解説しました。
まずは全体の流れをつかみ、できるところから一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。

目次
この記事を監修した弁護士
西田 幸広 法律事務所Si-Law代表
弁護士・法律事務所Si-Law/(株)TORUTE代表・西田幸広 熊本県を中心に企業顧問70社、月間取扱160件以上(2025年8月時点)。登録3,600社・20超業種を支援し、M&A・事業承継を強みとする。弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士の資格保有。YouTubeやメルマガで実務解説・監修/寄稿多数。LINE登録特典で「事業承継まるわかりマニュアル」提供。
事業承継と会社売却の違いとは
事業承継とは、会社の経営や想い、これまで築いてきた価値を次の世代へ引き継ぐことと考えます。
家族や社員に引き継ぐ場合もあれば、外部の人や他社に託す場合もあるでしょう。
単に会社の株や経営の権利を渡すだけでなく、取引先との関係や従業員の技術・経験など、会社の「中身ごと」受け渡すイメージです。
一方、会社売却はその方法のひとつで、会社や事業の一部を第三者に譲ることです。
つまり、事業承継が「会社をどう次につなぐか」という全体の考え方だとすれば、会社売却はそのなかで選べる具体的なやり方のひとつ、と考えるとわかりやすいでしょう。
以下の記事では、事業承継とM&Aの違いについても解説しています。
関連記事:事業承継とM&Aの違いは?メリットとデメリットや選び方のポイント・課題も徹底解説!
会社売却の2つの方法
会社売却の方法は、大きく分けて以下の2つがあります。
- 株式譲渡(株式を売る方法)
- 事業譲渡(事業だけを売る方法)
株式譲渡は会社そのものを丸ごと引き継ぐイメージであり、事業譲渡は必要な事業だけを選んで渡すイメージと考えると理解しやすいでしょう。
目的と状況に合わせて、どちらが合うかを見極めるところから始めるのがおすすめです。
株式譲渡
株式譲渡とは、社長などが持っている会社の株を買い手に渡し、会社の「持ち主」を交代する方法です。
会社そのものはそのまま残るため、取引先との契約や従業員の雇用も、基本的にはこれまでどおり続けられます。
手続きが比較的シンプルで、現場の混乱を少なくできるのが大きな特徴と言えるでしょう。
税金については、会社を売るのではなく「株を売って得た利益」に対して課税されます。
買い手は会社の借入金や将来のリスクも引き継ぐことになるため、事前に「デューデリジェンス(買収監査)」と呼ばれる詳細な調査をおこなうのが一般的です。
売る側としては会社の情報をできるだけ正直に伝え、約束する範囲や期間をしっかり決めておくことで、あとからトラブルになる心配を減らし、安心して引き渡しが進められるでしょう。
事業譲渡
事業譲渡とは、会社のなかから「売りたい部分」だけを選んで相手に渡す方法です。
例えば工場を例にすると、その設備・在庫・取引先との契約・商標や顧客情報などをひとまとめにして引き渡します。
この方法のよいところは、売りたい事業の範囲を自由に決められる点と言えるでしょう。
赤字の部門だけを手放したり、特定の商品グループをまとめて売ったりすることもできます。
ただし、取引先と契約を結び直し・必要な許可の取り直し・従業員への説明で同意をもらうなど、手続きが増える傾向があります。
誤解やトラブルを防ぐためには、従業員への説明を丁寧におこない、条件をきちんと書面で確認しておくなど、準備の段階から関係者で予定を立て、順を追って進めていくのがおすすめです。
事業承継のメリット
事業承継の大きなメリットは、会社の「らしさ」をそのまま次の世代へ引き継ぐことができる、ということだと考えます。
長年築いてきた取引先との信頼関係・地域で果たしてきた役割・社員の成長の流れなどを守りやすく、働く人たちの安心にもつながります。
あとを継ぐ相手が誰であれ、早めに準備を始めれば、後継者の育成・設備の更新・銀行との話し合い・個人保証の整理などを少しずつ進めていけるでしょう。
その結果、引き継ぎの間は顧問として関わりながら、ゆっくりと経営のバトンを渡していくことも可能です。
地域や家族から「良い引き継ぎだった」と言ってもらえるようにするためには、何よりも「時間の余裕」を持つことが大切ですので、焦らず段階を追って進めていきましょう。
事業承継のデメリットやリスク
事業承継には多くの良い面がありますが、同時に注意しておきたいデメリットやリスクもあります。
まず、準備不足のまま進めることが最大のリスクと考えます。
しっかりと計画を立てないと、後継者の判断が遅れたり社員の間で考えが食い違ったりして、会社の動きが鈍くなってしまいます。
誰がどの範囲まで決めてよいのかをはっきりさせないままだと、現場が混乱し、取引先からの信頼を損なうおそれもあるでしょう。
また、家族や社員に引き継ぐ場合は、お金や株の扱い・相続のことなどで話が複雑になりがちなため、うまく整理しないと家族間で意見がぶつかることもあります。
一方で外部の人に会社を譲る場合は、取引先や社員が「今後どうなるのだろう」と不安を感じることがあり、心理的なケアも必要です。
これらのリスクを防ぐためには、早めに準備を始め、信頼できる専門家の力を借りることが大切と言えるでしょう。
事業承継の全体像や手順などは、次の記事を参考にしてください。
関連記事:事業承継とは?基本的な考え方や支援制度・手順までをわかりやすく徹底解説!
また、事業承継で迷うことがある場合は、TORUTE株式会社にぜひご相談ください。

会社売却のメリット

会社を売却する最大の魅力は、後継者がいなくても事業を次の世代へつなげられることだと考えます。
これまで築いてきた会社の価値を活かしながら、自分の努力の成果をしっかりと形に残すことができるのです。
ここでは、会社売却のメリットを以下のようにまとめました。
- 主力事業に経営資源を集中できる
- 【株式譲渡の場合】手続きが簡単になる
- 【株式譲渡の場合】売却側の税負担が軽くなることがある
- 【事業譲渡の場合】売却範囲を柔軟に決められる
- 【事業譲渡の場合】不要なリスクを回避できる
それぞれについて、詳しく解説していきます。
主力事業に経営資源を集中できる
いくつかの事業を持つ会社では、あまり利益が出ていない部門を思い切って他社に譲り、その分の人や資金を主力事業に集中させることができるというメリットがあります。
事業を整理して力を注ぐ分野を決めると、会社が「これから何を大切にして進むのか」がはっきりします。
その結果、社員にも方向性が伝わりやすくなり、取引先や銀行にも安心感を与えられるでしょう。
一方買い手にとっても、すでに実績のある技術や顧客を引き継ぐことができるため、ゼロから始めるよりも短期間で事業を軌道に乗せやすいというメリットがあります。
お互いの思惑がうまく合えば、単に足し算のように規模を大きくするだけでなく、強みを掛け合わせて新しい成果を生み出すことも可能です。
業績が良いうちに検討を始めておくと、より有利な条件で話を進めやすくなるでしょう。
【株式譲渡の場合】手続きが簡単になる
株式譲渡の場合、メリットのひとつとして手続きが簡単になることが挙げられます。
会社の「株」をそのまま相手に渡す形になるため、会社そのものは変わらず、社名・契約・従業員の雇用関係も基本的にそのまま引き継がれます。
そのため、取引先との契約を一から結び直したり、従業員にあらためて同意をもらったりする必要がほとんどなく、手間や時間を大きく減らすことができるでしょう。
もちろん業種によっては行政への届け出や主要な取引先への説明が必要な場合もありますが、全体としては手続きの数が少なく、スムーズに進められるのが特徴と言えます。
忙しい経営者や、できるだけ社内外への影響を抑えて売却したい方にとって、株式譲渡は現実的で負担の少ない方法といえるでしょう。
【株式譲渡の場合】売却側の税負担が軽くなることがある
株式譲渡のもうひとつの大きなメリットは、売却側の税金が比較的軽くなることがあるという点です。
会社そのものを売るのではなく、「自分が持っている株」を買い手に渡す形になるため、税金は会社ではなく社長個人にかかります。
このときの税率は会社の利益にかかる税金よりも低く設定されており、一般的には所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%を合わせた約20.3%が目安です。
例えば会社をまるごと売るよりも、手元に残るお金である税引き後の金額が多くなる場合があるでしょう。
ただし、会社の状況や売却金額によって扱いが変わることもあるため、早めに税理士へ相談しておくと安心です。
参考:国税庁|株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
参考:国税庁|譲渡した株式等の取得費
【事業譲渡の場合】売却範囲を柔軟に決められる
事業譲渡の場合、「売却範囲を自分で自由に決められる」ことが大きなメリットだと考えます。
会社全体ではなく、たとえば「この工場だけ」「この商品だけ」といった形で、必要な部分だけを相手に渡すことができるのです。
また将来のリスクがありそうな契約や、手放したくない資産をあえて残すこともできるため、自社の事情に合わせた柔軟な調整ができます。
一方の買い手にとっても、欲しい技術や顧客などを狙って引き継げるため、両者にとって納得のいく形にしやすい方法と言えるでしょう。
ただし、どの部分を譲るかによっては契約のやり直しや相手の同意が必要になる場合もあります。
早い段階で全体の流れを整理し、関係者と丁寧に話を進めていくことが大切です。
【事業譲渡の場合】不要なリスクを回避できる
事業譲渡のもうひとつのメリットは、不要なリスクを回避できること、と考えます。
会社全体ではなく売りたい部分だけを選んで譲ることができるため、例えば「古い契約・使っていない設備・今後負担になりそうな借入れ」などを、あえて譲渡の対象から外すことができます。
このように引き継ぎたくないものを残しておけるので、売る側はすっきりと身軽になり、買う側も不要なリスクを抱えずに済みます。
お互いに安心して取引を進められる点が、この方法の大きな魅力と言えるでしょう。
ただしトラブルを避けるためにも、「何を渡し・何を残すか」を明確にして、相手ときちんと話し合っておくことが大切です。
会社売却のデメリットやリスク
会社売却には多くのメリットがありますが、その一方で注意しておきたいデメリットやリスクも存在します。
こうした点を理解せずに進めてしまうと、あとになって思わぬ負担やトラブルにつながることもあるでしょう。
会社売却のデメリットやリスクには、以下のようなものがあります。
- 【株式譲渡の場合】負債まで引き継ぐことになる
- 【事業譲渡の場合】手続きが煩雑化する傾向がある
- 【事業譲渡の場合】株式譲渡に比べて税負担がかかる
- 【事業譲渡の場合】譲渡後の事業に制限がかかる
安心して会社売却を進めるためにも、しっかりと対策をしていきましょう。
【株式譲渡の場合】負債まで引き継ぐことになる
株式譲渡では、会社にある資産だけでなく、借入金などの負債もすべて一緒に引き継がれます。
見えにくい将来のリスクや、過去の契約上の責任までも引き継がれる可能性がある点が注意すべきポイントと言えるでしょう。
そのため買い手は、契約や会計の内容を細かく確認し、問題がないかを徹底的に調べます。
売り手としても、会社の状況を正直に開示し、あとから「聞いていない」「話が違う」とならないようにしておくことが大切です。
もし隠していた負債やトラブルがあとで見つかると、損害の補償などで想定外の費用が発生するおそれがあります。
「隠さない・遅らせない・曖昧にしない」の3つを意識して、信頼を保ちながら交渉を進めるようにしましょう。
【事業譲渡の場合】手続きが煩雑化する傾向がある
事業譲渡は、手続きが複雑になりやすいというデメリットもあります。
例えば取引先との契約の再締結や、行政の許可を再取得する必要が出てくる場合があります。
また従業員を新しい会社に移すときには、仕事内容や待遇についてきちんと説明し、同意を得なければなりません。
このように、関係者ごとに確認や書類のやり取りが増えるため、全体の準備に時間と手間がかかります。
スムーズに進めるためには、早めに計画を立てて担当者を決め、専門家にも相談しながら進めるのがよいでしょう。
【事業譲渡の場合】株式譲渡に比べて税負担がかかる
事業譲渡では、株式譲渡に比べて税負担が重くなることがあります。
会社が持っている設備や在庫などの資産を売ったとみなされるため、その利益に対して法人税がかかるのです。
さらにそのお金を社長個人に配当などの形で移すと、もう一度税金がかかることになり、結果として手元に残る税引き後の金額が少なくなるケースがあります。
ただし、会社の赤字の状況や売却する資産の内容によっては、税金の額が変わることもあるでしょう。
早めに税理士に相談して、どのくらいの税金がかかるのかを試算してもらうと安心です。
【事業譲渡の場合】譲渡後の事業に制限がかかる
事業譲渡をおこなうと、売却したあとに同じような事業をすぐに始められなくなるという制限が設けられる場合があります。
これは買い手の会社が安心して事業を引き継げるようにするための取り決めで、「競業をしない・以前の取引先や社員を誘わない」などのルールが契約に盛り込まれることが多いでしょう。
ただしこの制限が長すぎたり、対象となる地域や事業の範囲が広すぎたりすると、将来また同じ分野で挑戦したいと思ったときに動きづらくなることがあります。
そのため、契約を結ぶときには、「どのくらいの期間・どの範囲で制限するのか」を現実的な内容に調整しておくことが大切です。
強すぎる制限も緩すぎる制限も問題になるため、買い手・売り手の双方が納得できる「ちょうどよいバランス」で決めておくと安心です。
事業譲渡の場合、従業員はどうなる?
事業譲渡では、従業員一人ひとりの同意を得て新しい会社に移ってもらうことが基本になります。
もし給与や勤務地など働く条件が変わる場合は、事前に十分な説明と話し合いをおこない、本人が納得したうえで進めることが大切です。
無理に進めたり、同意しなかったことを理由に不利な扱いをすることは認められていません。
円滑に進めるためには、待遇の見通しや新しい会社の紹介など、安心できる情報を丁寧に伝えましょう。
経営者自身の言葉で気持ちを伝えることで、従業員の不安を和らげ、信頼を保ちながら引き継ぎを進められるはずです。
株式譲渡の場合、従業員はどうなる?
株式譲渡の場合、従業員の雇用契約は会社にそのまま残るため、基本的には今までと同じ条件で働き続けることができます。
ただし、社名の変更や新しい体制への切り替えで、社員のなかには不安を感じる人も出てくるかもしれません。
法律上は特別な手続きや再契約は不要ですが、だからこそ経営方針・待遇の見通し・評価や昇給の考え方を早い段階で丁寧に伝えることが大切です。
買い手側の会社の雰囲気や考え方を具体的に共有し、現場の声を聞く場を設けておくとよいでしょう。
こうしたコミュニケーションを重ねることで、従業員の不安が和らぎ、結果として離職のリスクを減らすことにもつながります。
大切な従業員だからこそ、不安のない状態でともに次のステップに進みたいですよね。
悩むことがある場合は、一度TORUTE株式会社にご相談ください。

事業譲渡か株式譲渡かを選ぶ5つのポイント

事業譲渡と株式譲渡は、どちらが正しいというものではなく、会社の状況や目的によって最適な答えが変わります。
まずは判断の基準をはっきりさせたうえで、それぞれの方法を落ち着いて比較してみることが大切です。
検討の際は、次の5つのポイントで整理すると考えやすくなるでしょう。
- 譲渡の範囲
- 税金
- 負債・リスクの引き継ぎ
- 従業員の処遇
- 契約などの手続き
売却価格だけではなく、「従業員の雇用を守れるか・個人保証を外せるか・自分がどのくらい関わり続けるか」といった要素も交渉の条件に含めると、後悔のない形でまとめやすくなるはずです。
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
譲渡の範囲
ひとつ目のポイントは、譲渡の範囲です。
どこまでを売るか、そして何を残すかによって、最適な方法は変わります。
例えば古い設備や使っていない土地など、不要な資産や将来のリスクを手放したい場合は「事業譲渡」が向いています。
一方で、会社全体をそのまま引き継ぎ、取引先や社員への影響をできるだけ少なくしたい場合は「株式譲渡」を選ぶほうがスムーズと言えるでしょう。
まずは、「どの資産や契約や人材を移すのか・どの部分は残すのか」を整理し、優先順位を決めるのがおすすめです。
また、安定した利益を生む取引先や今後の成長につながる事業の組み合わせなど、買い手にとって魅力的に見えるポイントを意識して範囲を決めると、売却価格や条件の交渉を有利に進めやすくなるでしょう。
税金
次に、税金面も判断の大切なポイントです。
株式譲渡と事業譲渡ではかかる税金の仕組みが違うため、最終的に手元に残る金額にも差が出ることがあるでしょう。
株式譲渡では、社長個人が持っている「株」を売る形になるため、税金は社長個人にかかります。
一方、事業譲渡は会社が持つ設備や資産を売ることになるため税金は会社にかかり、そのあとお金を社長個人に移すと、さらにもう一度税金が発生する場合があります。
このように、どちらの方法を選ぶかで手取り額が変わることがあるため、事前に税理士へ相談し、2つ以上のパターンで税金を試算してもらうのがおすすめです。
税率だけでなく、会社の赤字や資産の内容によって結果が大きく変わることもあるため、数字で比較しながらじっくり判断するようにしましょう。
負債・リスクの引き継ぎ
会社を売却する際に気をつけたいのが、借入金や将来のトラブルなど、目に見えにくいリスクをどう扱うかという点です。
株式譲渡の場合は、会社そのものをそのまま引き継ぐため、資産だけでなく負債や将来の責任も一緒に移る形になります。
このため買い手は契約内容や財務状況を細かく確認し、問題がないかを徹底的に調べますし、売り手としては会社の実情を正直に開示し、信頼を得ることが何より大切です。
一方、事業譲渡では引き継ぐ部分を選べるため、不要な負債やリスクを対象から外すことが可能です。
ただし、買い手から見ると「本当に大丈夫か」と不安を感じやすい面もあるため、事前に丁寧な説明と合意をしておくとよいでしょう。
お互いの安心のために、「どこまで引き継ぐのか・どこは残すのか」を明確にし、契約内容を慎重に整えておくことが重要と言えます。
従業員の処遇
従業員の処遇も大切なポイントと考えます。
従業員の安心を守るために、まず大切なのは「これからも安心して働ける」という見通しを示すことです。
株式譲渡の場合は会社そのものがそのまま残るため、基本的に雇用条件は変わりませんが、評価制度や給与体系の運用が変わることもあるため、社員が戸惑わないように丁寧に説明しておくとよいでしょう。
一方で事業譲渡は、従業員ごとに同意を得て新しい会社に移る必要があります。
待遇・勤務地・仕事内容の見通しをしっかり伝え、書面にまとめて合意を得るのがおすすめです。
また、労働組合や代表社員と事前に話し合いの場を持っておくと、会社への信頼を保ちながらスムーズに進められるでしょう。
契約などの手続き
最後に、契約などの手続きです。
株式譲渡の場合は、会社そのものが変わらないため、契約や許可関係は基本的にそのまま引き継がれます。
そのため、取引先や関係機関への説明をおこなうだけで済むケースが多く、手続きの負担は比較的軽くなるでしょう。
一方、事業譲渡では売る部分だけを切り分けて渡すため、契約の結び直し・行政への再申請・商標や特許などの名義変更といった作業が必要になることがあります。
こうした手続きが重なると時間がかかるため、早めに計画を立てておくのがおすすめです。
手続きをスムーズに進めるために工程表を作って担当者と期限を明確にし、税理士や弁護士などの専門家と定期的に進捗を確認していくようにすると、遅れや漏れを最小限に抑えることができるでしょう。
事業売却は個人事業主でも可能?
個人事業の場合でも、顧客・在庫・設備・商標・ノウハウなどをまとめて第三者に引き継ぐことはできます。
法人のように株式という仕組みがないため、基本的には「事業譲渡」という形でおこなうのが一般的です。
税金の扱いは譲る資産の内容や所得の種類によって変わり、どのように売却金額を分けるかによっても税額に差が出ることがありますので、事前に専門家へ相談しておくのがよいでしょう。
また買い手に安心してもらうためには、売上や利益の流れが安定していること・事業が経営者個人に依存しすぎていないことを、資料などでわかりやすく示すことが大切と言えます。
まずは帳簿の整理や、業務の流れを「見える化」することから始めるのがおすすめです。
事業売却は儲かる?
「事業売却が儲かるかどうか」は、売却益の金額だけでなく、税引後の手取りや売却後の人生設計まで含めるべきテーマだと考えます。
会社の価格は、今後も安定して利益を出せるかどうかや、買い手との相性によって決まります。
自社の強みや実績を正しく伝え、買い手が安心できるように情報を開示しておくと、評価が高まりやすくなるでしょう。
反対に、節税だけを目的にしてしまうと、取引そのものへの信頼を損ねかねません。
税金は「負担」でもありますが、将来の安心を得るための必要なコストでもあります。
税務・法務・労務・会計といった複数の視点から、全体としてどの方法が一番得なのかを冷静に見極めることで、最終的に満足度の高い結論へとつながるでしょう。
0円会社譲渡とは?
0円会社譲渡とは、赤字や借金を抱えた会社を無償で引き渡し、その代わりに買い手が借入金や再建にかかる費用を引き受ける取引のことです。
もし「会社を手放したいが清算までは避けたい」「従業員の雇用をできるだけ守りたい」と考えているのであれば、この方法が選択肢のひとつとして考えられるでしょう。
清算費用を抑えられる可能性があり、事業を誰かに引き継ぐことができる点がメリットです。
ただし、引き渡したあとにどこまで責任を負うのか・経営者保証をどう扱うのかなど、契約内容を細かく決めておかないとトラブルの原因になります。
再建計画の中身がしっかりしているか、金融機関や取引先が納得しているかも重要と言えるでしょう。
焦って決断するのではなく、専門家や公的支援制度を活用しながら、安心できる形で進めることをおすすめします。
会社売却をお考えの場合は「TORUTE株式会社」にご相談を

事業承継や会社売却は、経営者にとって人生の大きな節目です。
大切なのは、単に「いくらで売れるか」だけでなく、社員の雇用・取引先との関係・地域やご家族への想い、そしてご自身のこれからの生き方をどう守りながら次の一歩を踏み出すかという点だと考えます。
TORUTE株式会社は、そうした中小企業の現実に寄り添い、秘密を厳守したうえで事業承継と会社売却の両面から最適な解決策を提案させていただくことが可能です。
目的の整理・税後の試算・工程表の素案などといった初期診断から、買い手候補の探索・条件交渉・契約や引継ぎ支援まで、ワンストップで伴走いたします。
また、引継ぎ後の関係づくりやコミュニケーションの設計まで丁寧にサポートしますので、安心してお任せください。
「事業承継に役立つ無料マニュアル【完全版】」もプレゼントしておりますので、一度ご覧いただけますと幸いです。
一緒に、会社の未来とそこに関わる人たちの笑顔を守る、最善の道を見つけていきましょう。
\事業承継マニュアル無料プレゼント!/
まとめ
事業承継とは、会社の想いと価値を次の世代へつなぐための道筋です。
そのなかで会社売却は、後継者がいない場合などに有効な選択肢のひとつと言えるでしょう。
株式譲渡であれば、手続きが比較的シンプルで、契約や雇用関係もそのまま引き継がれます。
一方、事業譲渡は譲る範囲を自由に決められるため、不要な資産やリスクを切り離しやすいのが特徴です。
最終的には「価格」だけでなく、雇用・取引先・ご家族・そしてご自身の今後を含めた総合的な条件で判断することが大切になります。
数字だけにとらわれず、心から納得できる形で次の世代へバトンを渡せるように準備を進めましょう。

まずはお気軽にご連絡ください
受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)
事務所概要
熊本
熊本市東区桜木3-1-30 ヴィラSAWADA NO.6 102号室
福岡
福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F
コラム一覧
- 2026年1月14日熊本で事業承継をお考えの方!支援制度や補助金・相談先と進め方までを専門家がわかりやすく解説!
- 2026年1月14日事業承継特別保証制度とは?メリット・デメリットや要件・申請方法もまとめて紹介!
- 2026年1月7日事業承継で専門家が必要な理由は?選び方やタイミング・補助金は使えるのかも解説!
- 2026年1月7日事業承継の株式譲渡の方法は?メリットや手続き方法・税金の特例制度についても解説!
- 2025年12月31日事業承継の株価対策とは?3つの評価方式や自社株の引き下げ対策をまとめて解説!
- 2025年12月31日承継会社とは?分割会社との違いや手続き方法・メリットとデメリットもわかりやすく解説!
- 2025年12月24日事業承継補助金の対象経費は?枠組みごとのルールや金額・認められない例も紹介!
- 2025年12月24日事業承継税制の延長はいつまで?提出期限のスケジュールや緩和要件についても解説!
- 2025年12月17日事業承継補助金は親子間でも対象?要件や申請方法・利用するときの難易度も解説!
- 2025年12月17日事業承継の手順は?引き継ぐ3つの要素や必要書類・受けられるサポートもまとめて紹介!
- 2025年12月10日事業承継と相続との違いは?税制の対象や手続き方法・起こりやすいリスクも紹介!
- 2025年12月10日事業承継の税制優遇とは?制度の内容や期限・使えないケースについても徹底解説!
- 2025年11月27日事業承継の費用の相場はどれくらい?税金対策や補助金・誰が負担するのかも解説!
- 2025年11月27日事業承継と会社売却の違いは?メリット・デメリットや従業員はどうなるのかも徹底解説!
- 2025年11月27日事業承継後のトラブルで起こりやすい事例は?原因や対応策・成功例までまとめて紹介!
- 2025年11月27日事業承継の相談先10選を紹介!相談費用は無料なのか・選び方のポイントも解説!
- 2025年11月26日事業承継の企業価値とは?算出方法や3つのアプローチ・高値がつくケースも解説!
- 2025年11月26日事業承継の後継者不足の原因は?担い手がいない理由や解決策・成功例まで紹介!
- 2025年11月26日中小企業の事業承継問題とは?課題や問題点・具体例についてもわかりやすく紹介!
- 2025年11月25日事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!
- 2025年11月25日事業承継の補助金や助成金は?2025年度はいくらもらえるのか・対象経費も解説!
- 2025年11月25日事業承継の手続きで法人の場合の流れは?必要書類や税金などの費用・補助金もまとめて解説!
- 2025年11月24日事業承継に使える補助金は?2025年度のスケジュールや申請方法・対象経費なども解説!
- 2025年11月24日事業承継でやるべきことリストを紹介!必要な知識や書類・課題についても解説!
- 2025年11月24日事業承継ファンドとは?活用が有効なケースやメリット・デメリットも紹介!
- 2025年11月23日事業承継税制の要件とは?特例措置と一般措置の違いやメリット・デメリットも解説
- 2025年11月23日事業承継とM&Aの違いは?メリットとデメリットや選び方のポイント・課題も徹底解説!
- 2025年11月23日事業承継とは?基本的な考え方や支援制度・手順までをわかりやすく徹底解説!
- 2025年3月14日親の会社を継ぐメリットやデメリットとは?引き継ぐポイントなど
- 2025年3月7日企業価値を高める5つの方法|メリットや評価方法なども解説
- 2025年2月14日事業承継対策の方法とは|必要性や流れ、成功のポイントなど
- 2024年12月6日事業承継は弁護士へ相談すべき?役割や費用相場、選び方など
- 2024年11月22日事業承継のマッチング支援とは?利用するメリット・デメリットなど
- 2024年11月1日事業承継と廃業はどちらを選ぶべき?それぞれのメリット・デメリットなど
- 2024年10月25日経営承継円滑化法とは?事業承継で活用できる支援制度をわかりやすく解説
- 2024年10月11日事業承継における11の失敗事例|原因や成功させるポイントを詳しく解説
- 2024年9月20日事業譲渡における従業員への影響|退職金の扱いや注意点などを詳しく解説
- 2024年7月5日事業承継ガイドラインとは?概要や策定の背景をわかりやすく解説
- 2024年6月14日農業を事業承継するには?方法や成功に導くためのポイントを解説
- 2024年6月7日事業承継の計画について|策定の手順・ポイントや計画書の書き方
- 2024年5月31日事業承継における中小企業の現状や課題は?解決策とともに弁護士が解説
- 2024年5月24日事業承継のための融資「事業承継ローン」の種類や利用の流れについて
- 2024年5月2日相続対策としての事業承継|事業承継税制などの相続税対策も解説
カテゴリー一覧
タグ