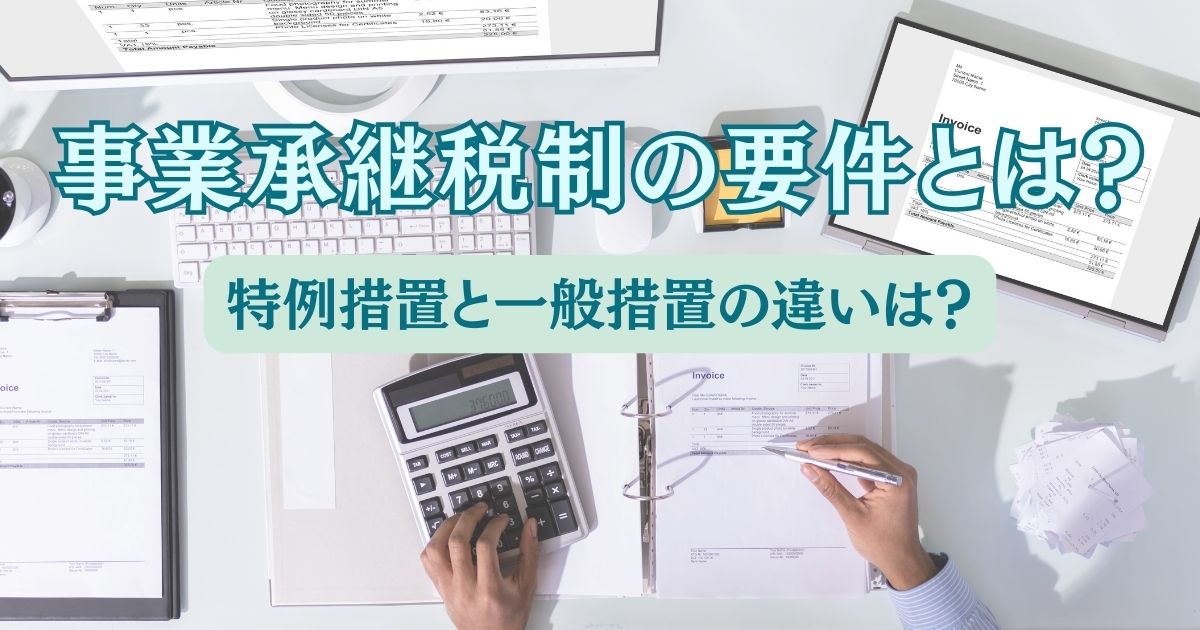事業承継税制の要件は、「いざ承継を進めよう」と思い立ってからでは間に合わない項目が多く、先に全体像を押さえることが重要です。
特に、制度の柱である「特例措置」を使うか「一般措置」で進めるかで準備内容が変わります。
とはいえ、事業承継税制の要件の細目は複雑で、「自社は対象になるのか」「期限はいつまでか」「雇用や役員就任の要件は?」と不安になりがちです。
本記事では、要件をチェックリスト化し、特例措置と一般措置の違いやメリット・デメリット、手続きの流れと注意点まで、経営者の方が今すぐ判断・着手できるレベルで整理して解説します。

目次
この記事を監修した弁護士
西田 幸広 法律事務所Si-Law代表
弁護士・法律事務所Si-Law/(株)TORUTE代表・西田幸広 熊本県を中心に企業顧問70社、月間取扱160件以上(2025年8月時点)。登録3,600社・20超業種を支援し、M&A・事業承継を強みとする。弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士の資格保有。YouTubeやメルマガで実務解説・監修/寄稿多数。LINE登録特典で「事業承継まるわかりマニュアル」提供。
事業承継税制とは
事業承継税制とは、非上場株式を後継者が相続・贈与で取得する際の相続税・贈与税の納税を猶予し、一定の要件を満たせば最終的に免除まで見込める制度です。
この税制には、通常の一般措置に加え、優遇された特例措置があります。
特例措置は、猶予される株式の割合や後継者の人数などで一般措置よりも優れており、大幅な税負担の軽減が期待できます。
特例措置を活用するには、事前に「特例承継計画」を提出し、都道府県からの認定(円滑化法の認定)を受ける必要があります。
事業承継税制は、税負担を一時的に猶予することで資金繰りを安定させ、円滑な事業承継を可能にする「安全弁」のような役割を果たしてくれる制度です。
事業承継税制のメリット
事業承継税制の最大のメリットは、税負担の平準化です。
特例措置なら贈与・相続とも猶予割合100%(税額全額の支払い猶予)かつ全株式が対象になり、最大3人の後継者に分けて承継する設計も可能です。
さらに雇用確保要件(従業員数を維持する義務)が柔軟化されたため、万が一、要件を達成できなくても、報告や確認をすることで猶予が継続できる余地があります。
これにより、株式移転のタイミングを事業計画と連動させやすく、納税に回すはずだった資金を成長投資や人材に回す余力が生まれます。
結果として、後継者の心理的負担も軽くなり、組織を混乱なくスムーズに着地させることが可能です。
事業承継税制のデメリット
事業承継税制は有利な制度ではありますが、以下のようなデメリットもあるため注意が必要です。
1.時間的な制約がある
特例承継計画の提出期限や制度の実施期限など、定められた期間内に手続きを進めなければならないという時間的な制約があります。
2.継続的な管理と要件遵守が必要
制度の適用を受けている間は、事業の継続、代表者の在任、株式の保有といった継続的な要件を守る必要があります。
また、担保の提供や、定期的な報告(継続届出)といった事務作業も欠かせません。
3.要件違反で多額の負担が発生する
もし途中で要件を満たせなくなったり、株式を第三者に譲渡したりした場合、猶予されていた税額に加え、多額の利子税も合わせて支払うことになります。
有利な反面、継続的な管理が欠かせない制度と捉えると判断しやすくなります。
参考:国税庁|事業承継税制特集
事業承継税制の要件とは?
事業承継税制の要件は、大きく以下の4領域に分かれます。
- 会社に関する要件
- 先代経営者に関する要件
- 後継者に関する要件
- 納税猶予期間中の事業継続に関する要件
ここでは、それぞれの要点をチェックリストにまとめてご紹介します。
会社に関する要件チェックリスト
- 自社が中小企業者に該当し、上場会社ではない
- 資産管理会社や風俗営業会社に該当しない
- 議決権制限のない非上場株式である
【特例措置の場合】
- 特例承継計画を策定し、認定支援機関の所見を付して期限内に都道府県へ提出している
- 円滑化法の認定を取得している
これらは前提となる重要事項であり、ここでの判断を誤ると、その後のすべての計画や施策が無効化されてしまう可能性があります。
まずは自社が当てはまるかを最初にしっかりと確認しましょう。
先代経営者に関する要件チェックリスト
- 過去に代表権を有していた
- 承継直前に同族関係者と合わせて議決権50%超を保有し、かつその中の筆頭株主であった
- 贈与・相続時点では代表権を有していない
事業承継の肝は、税制適用の「主導権の移転」となるため、後継者への権限集中を明確にしておくほど手続きがスムーズになります。
手続きの期限やスケジュール管理については、顧問税理士や司法書士とチームとなって進めるのがおすすめです。
後継者に関する要件チェックリスト
- 代表権を有する
- 18歳以上である
【令和7年度税制改正後】
- 贈与の直前に役員である(従来の「3年以上役員」から見直し)
- 同族関係者と50%超の議決権を保有し、筆頭株主要件を充足する
さらに特例措置では、後継者が取得する株式の数に下限が定められています(例:一人の後継者が承継する場合、発行済み株式総数の3分の2から既に保有している株式数を引いた数以上)。
役員在任期間の緩和により、承継計画の策定と株式の移転をスムーズに同時進行できるようになっています。
納税猶予期間中の事業継続に関する要件チェックリスト
【経営(贈与・相続)承継期間の5年間】
- 税務署への継続届出と都道府県への年次報告が必要
【経営(贈与・相続)承継期間から5年経過後】
- 都道府県への年次報告は不要
- 税務署へ3年ごとのに継続届出が必要
制度の適用を受けている間は、事業継続・代表者継続・株式保有継続や担保提供の維持など、基本的な要件は絶対に崩さない運用が前提です。
もし報告漏れがあった場合は、納税猶予が打ち切られる重大な原因になりかねません。
参考:国税庁|非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
事業承継税制の筆頭要件は?

事業承継税制の実務上の筆頭要件は、「特例承継計画の期限内提出」と「都道府県の認定取得」です。
これがないと特例措置は使えず、猶予割合・対象株数・後継者数などの優遇を失います。
提出期限は2026年3月末、特例の適用対象となる承継の実施期限は2027年12月31日です。
期限や詳細などは今後も改訂される可能性があるため、都度確認するようにしましょう。
一連の手続きは、以下のようなステップで進めます。
- 1.認定経営革新等支援機関との相談
- 2.特例承継計画の作成・都道府県への提出
- 3.都道府県知事による認定
- 4.贈与・相続の実行
- 5.税務署への申告書提出
まずは計画を立て、認定を受け、最後に承継するというステップで進めます。
この流れを基準に、完了日から逆算して、後継者の役員就任や株式の移動日を早めに決めるのがおすすめです。
事業承継税制の特例措置とは
事業承継税制の特例措置は、2018年度の改正により10年間限定で拡充された仕組みです。
- 全株式が対象
- 猶予割合100%(税額全額の支払い猶予)
- 最大3人の後継者に承継可能
- 雇用要件の弾力化
などの優遇があります。
一方で、特例承継計画の提出と適用期限はセットです。
言い換えると、例措置は非常に強力な優遇策である代わりに、定められた期限と厳格な手続きを守る覚悟が求められる制度だということです。
これを前提に、次は一般措置との違いを解説します。
特例措置と一般措置の違い
特例措置と一般措置の主な違いは、以下の内容です。
自社の株主構成や後継モデルに応じ、設計自由度を評価軸に選択します。
| 一般措置 | 特例措置 | メリット (特例措置の優位点) | |
|---|---|---|---|
| 事前計画の要否 | 原則不要 | 特例承継計画の提出が必須 | 認定を得ることで、優遇された制度を利用できる |
| 適用期限 | 期限の定めなし | 2027年12月31日まで | 時限的な拡充であり、適用を急ぐ必要がある |
| 対象株数 | 最大3分の2 | 全株式(100%) | 後継者が会社の全支配権を得やすくなる |
| 猶予割合 | 相続:80%贈与:100% | 100%(税額全額猶予) | 税負担を最大限に回避でき、資金繰りが安定する |
| 後継者数 | 1人のみ | 最大3人まで | 複数の親族や役員に株式を分散して承継できる |
| 雇用要件 | 原則維持 | 弾力化(未達でも継続の余地あり) | 事業環境の変化に柔軟に対応でき、要件違反のリスクが低い |
以下の記事でも、事業承継の税制優遇についてまとめています。
関連記事:事業承継の税制優遇とは?制度の内容や期限・使えないケースについても徹底解説!
事業承継税制の特例措置のメリット・デメリット
事業承継税制の特例措置のメリットは、以下の3つです。
- 100%の猶予と全株式対象による資金負担を極小化できる
- 3人承継での柔軟設計ができる
- 雇用要件の弾力化ができる
またデメリットには、以下のようなものがあります。
- 計画提出・認定の事前手続きが必要
- 期限管理が必要
- 担保提供や継続届出にの運用負荷がかかる
- 要件不充足時のリスクがある(猶予打ち切り・利子税)
事業承継は、早く動きだすほど、利用できる優遇措置や選択肢が増えます。
そのため、年内に全体の工程表を作ることが、最も費用対効果の高い最初の一手と言えるでしょう。
事業承継税制の特例措置は延長される?
2025年11月時点での特例承継計画の提出期限は2026年3月31日まで、承継の実施期限は2027年12月31日までと示されています。
2025年度税制改正では、後継者の役員就任要件が「贈与の直前までに役員」へと大幅に緩和された一方、適用期限の延長は盛り込まれていません。
したがって、現行の期限に間に合うよう、計画を前倒しで実行することが重要と言えます。
事業承継税制の延長については、以下の記事でも解説しています。
関連記事:事業承継税制の延長はいつまで?提出期限のスケジュールや緩和要件についても解説!
適用期限や要件については今後の改正で変わる可能性もあるため、最新の一次情報を必ず確認してください。

事業承継税制で5年経過後はどうなる?
事業承継税制は承継後5年が経過すると、提出義務などが一部緩和されます。
継続される内容もあるため、しっかりと内容を把握しておくことが重要です。
ここでは、事業承継税制で5年経過後に「緩和される要件」と「継続される要件」をそれぞれご紹介します。
緩和される要件
承継後5年間は、都道府県への年次報告と税務署への継続届出が必要です。
5年を過ぎると、都道府県の年次報告は不要になり、税務署へ3年ごとに継続届出をおこなう体制へ移行します。
報告頻度が「年1回」から「3年に1回」に緩和されることで、管理の事務負担は確実に軽くなります。
また、特例措置では雇用要件(従業員数の維持義務)が柔軟に運用されるため、目標を達成できない年があっても、所定の報告と確認をおこなうことで納税猶予が継続できる余地があります。
制度の運用フェーズでは、組織変更や役員改選のスケジュールと、税務署等への報告のタイミングが一致しているかを常に確認するようにしましょう。
継続される要件
事業承継税制では承継後5年が経過しても、以下のような猶予の前提となる要件は基本的に継続します。
- 事業の継続
- 後継者が代表者であること
- 株式保有の継続
- 担保の維持 など
継続届出では、この前提が満たされているかを立証する書類の整備が欠かせません。
株式の譲渡・合併・解散など資本・組織に関わるイベントの前には、猶予への影響を必ず検討し、事前相談をおこなうのが安全です。
特に承継後の会社分割や合併などの事業形態変更には厳格な制限があり、事前の確認・承認なく実行すると猶予打ち切りとなるリスクがあります。
事業承継税制は最終的にどうなるの?
事業承継税制の猶予は、後継者の死亡や免除対象贈与など一定の事由が生じたときに免除されます。
逆に制度の要件を満たせなくなった場合(後継者が代表権を失う・株式を第三者に譲渡する・会社が解散するなど)は猶予打ち切りとなり、猶予税額+利子税の納付が必要です。
言い換えるとこの制度は、「最後まで事業を継続する」か「途中でやめて税金を払う」かの二択で設計されています。
将来のM&Aや組織再編をおこなう可能性も考慮して、免除・打ち切りのシナリオもあらかじめ計画に組み込んでおくのがおすすめです。
参考:国税庁|非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
事業承継税制の手続きの流れ

事業承継税制の手続きの基本的な流れは、以下のようになります。
- 特例承継計画の策定・提出
- 都道府県の認定(円滑化法12条)
- 贈与または相続の実行
- 申告期限までに申告・担保提供
- 納税猶予の開始
- 年次報告・継続届出
各工程は期限と必要書類が明確に定められ、順番を飛ばすことはできません。
全体のスケジュールを月ごとに細分化し、役員の就任日や株主総会・登記・申告などの重要タスクの期日から逆算して準備を進めることが、成功への近道です。
参考:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)
参考:中小企業庁|経営承継円滑化法申請マニュアル
また、相続税の場合と贈与税の場合では注意点があるため、それぞれご紹介します。
相続税の場合
相続発生後、相続税の申告期限(原則10か月)までに申告し、円滑化法の認定や担保提供をおこないます。
特例・一般いずれでも会社・後継者・先代要件を満たすことが前提です。
遺産分割・議決権構成・代表権の承継を並行で進め、筆頭株主・代表権のクリアを確認します。
相続は時間が短く、遺産評価や遺留分調整が絡むため、生前贈与・種類株・持株会なども含めた事前設計が要となります。
贈与税の場合
贈与税申告期限(翌年の3月15日)までに申告し、担保提供と必要書類の提出をおこないます。
特例では特例承継計画の提出が前提で、認定申請は贈与年の翌年1月15日までが目安です。
2025年度の改正により、後継者が役員に就任している必要のある期間が大幅に緩和され、「贈与の直前に役員になっていればよい」となりました。
これにより、後継者が役員に就任してから実際に承継するまでの期間を短縮できるようになっています。
実際の贈与実行日は、議事録・登記・持株比率に食い違いがないかを厳密に確認しましょう。
その上で、株価評価額・贈与契約書・資金の移動記録がすべて揃い、手続きの正当性を証明できるようにしてください。
参考:国税庁|贈与税の申告と納税
参考:国税庁|非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
事業承継税制の注意点とは
事業承継税制では、以下の点に注意が必要です。
- 株価評価の変動
- 担保提供の範囲
- 雇用・事業計画との整合
- 組織再編・M&Aの影響
- 継続届出の失念
これらは典型的な落とし穴です。
事業承継税制は5年間の年次報告義務があり、虚偽の報告や要件不充足が判明した場合は制度取消の対象となります。
特に要件不充足で猶予打ち切りとなると、猶予税額+利子税の負担が発生します。
制度は使うこと以上に使い続けることが重要です。
少なくとも3か月に一度(四半期ごと)は、役員変更・人事異動・株主構成の変化・設備投資などの重要な社内イベントが、税制の適用要件と食い違っていないかを点検する運用ルールを作るようにしてください。
事業承継税制のサポートは「TORUTE株式会社」へ

事業承継税制は、自社株の相続や贈与にかかる税負担を大幅に軽減できる一方、特例承継計画の提出期限や継続要件など、細かな条件を満たさなければ適用が認められない非常に複雑な制度です。
要件の見落としや手続きの遅れは、せっかくの優遇措置を無駄にしてしまうリスクにもつながります。
TORUTE株式会社では、税務だけでなく相続や会社法務に精通した弁護士が担当し、経営者様の状況に応じた最適な承継スキームの提案が可能です。
税理士や会計士とも連携しながら、制度の活用から契約・登記までしっかりとサポートいたします。
安心して次世代へ会社を引き継ぐために、まずはお気軽にご相談ください。
\事業承継マニュアル無料プレゼント!/
まとめ
事業承継税制の要件は、会社・先代・後継者・継続要件の4点セットで成立します。
特例措置は強力ですが、特例承継計画の提出(2026年3月末)と実施期限(2027年末)の管理が生命線です。
2025年度の改正で役員就任要件は緩和され、工程設計の自由度が増しました。
まずは会社・先代・後継者の現況で「何が足りないか」を棚卸しし、逆算の工程表を作成するのがおすすめです。
迷う点がある場合は、一次情報を基に専門家へ早めに相談するのが近道になります。

まずはお気軽にご連絡ください
受付時間/AM8:30~PM5:30(土日・祝休)

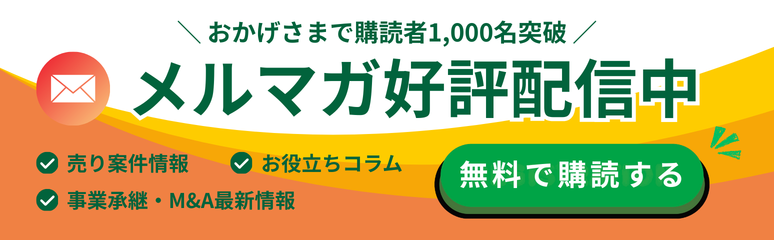 コラム一覧に戻る
コラム一覧に戻る
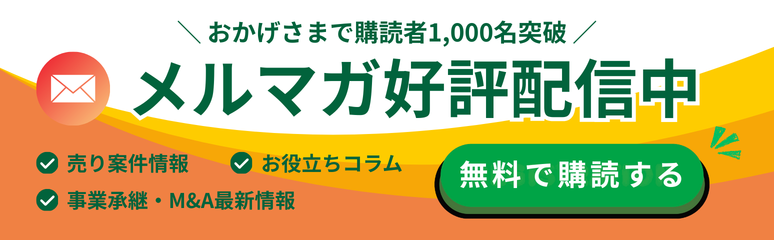
事務所概要
熊本
熊本市東区桜木3-1-30 ヴィラSAWADA NO.6 102号室
福岡
福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F
コラム一覧
- 2026年2月11日後継者不足の農業家ができる対策は?担い手減少の現状や原因・解決の手順を徹底解説!
- 2026年2月11日事業承継のリスクとは?具体例や放置するデメリット・回避して成功させるポイントも解説!
- 2026年2月4日事業承継の悩み13選!後継者が抱えやすい不安や問題の解決策も徹底解説
- 2026年2月4日事業承継の注意点や起きやすい問題を解説!事前準備や相談すべき相手もご紹介
- 2026年1月28日長崎県での事業承継をお考えの方!支援制度や成功のポイント・M&Aの注意点も解説!
- 2026年1月28日佐賀県での事業承継にお悩みの方!支援メニューや奨励金・相談窓口とその費用も解説!
- 2026年1月21日大分県で事業承継をお考えの中小企業は必見!進め方や支援メニュー・相談先をまとめて紹介!
- 2026年1月21日九州地方で事業承継を成功させるには?7県の特徴や支援制度・広がるM&Aの動きも解説!
- 2026年1月14日熊本で事業承継をお考えの方!支援制度や補助金・相談先と進め方までを専門家がわかりやすく解説!
- 2026年1月14日事業承継特別保証制度とは?メリット・デメリットや要件・申請方法もまとめて紹介!
- 2026年1月7日事業承継で専門家が必要な理由は?選び方やタイミング・補助金は使えるのかも解説!
- 2026年1月7日事業承継の株式譲渡の方法は?メリットや手続き方法・税金の特例制度についても解説!
- 2025年12月31日事業承継の株価対策とは?3つの評価方式や自社株の引き下げ対策をまとめて解説!
- 2025年12月31日承継会社とは?分割会社との違いや手続き方法・メリットとデメリットもわかりやすく解説!
- 2025年12月24日事業承継補助金の対象経費は?枠組みごとのルールや金額・認められない例も紹介!
- 2025年12月24日事業承継税制の延長はいつまで?提出期限のスケジュールや緩和要件についても解説!
- 2025年12月17日事業承継補助金は親子間でも対象?要件や申請方法・利用するときの難易度も解説!
- 2025年12月17日事業承継の手順は?引き継ぐ3つの要素や必要書類・受けられるサポートもまとめて紹介!
- 2025年12月10日事業承継と相続との違いは?税制の対象や手続き方法・起こりやすいリスクも紹介!
- 2025年12月10日事業承継の税制優遇とは?制度の内容や期限・使えないケースについても徹底解説!
- 2025年11月27日事業承継の費用の相場はどれくらい?税金対策や補助金・誰が負担するのかも解説!
- 2025年11月27日事業承継と会社売却の違いは?メリット・デメリットや従業員はどうなるのかも徹底解説!
- 2025年11月27日事業承継後のトラブルで起こりやすい事例は?原因や対応策・成功例までまとめて紹介!
- 2025年11月27日事業承継の相談先10選を紹介!相談費用は無料なのか・選び方のポイントも解説!
- 2025年11月26日事業承継の企業価値とは?算出方法や3つのアプローチ・高値がつくケースも解説!
- 2025年11月26日事業承継の後継者不足の原因は?担い手がいない理由や解決策・成功例まで紹介!
- 2025年11月26日中小企業の事業承継問題とは?課題や問題点・具体例についてもわかりやすく紹介!
- 2025年11月25日事業承継の後継者不在の現状は?年代・業界別の問題や原因・解決策もまとめて解説!
- 2025年11月25日事業承継の補助金や助成金は?2025年度はいくらもらえるのか・対象経費も解説!
- 2025年11月25日事業承継の手続きで法人の場合の流れは?必要書類や税金などの費用・補助金もまとめて解説!
- 2025年11月24日事業承継に使える補助金は?2025年度のスケジュールや申請方法・対象経費なども解説!
- 2025年11月24日事業承継でやるべきことリストを紹介!必要な知識や書類・課題についても解説!
- 2025年11月24日事業承継ファンドとは?活用が有効なケースやメリット・デメリットも紹介!
- 2025年11月23日事業承継税制の要件とは?特例措置と一般措置の違いやメリット・デメリットも解説
- 2025年11月23日事業承継とM&Aの違いは?メリットとデメリットや選び方のポイント・課題も徹底解説!
- 2025年11月23日事業承継とは?基本的な考え方や支援制度・手順までをわかりやすく徹底解説!
- 2025年3月7日企業価値を高める5つの方法|メリットや評価方法なども解説
- 2025年2月14日事業承継対策の方法とは|必要性や流れ、成功のポイントなど
- 2024年12月6日事業承継は弁護士へ相談すべき?役割や費用相場、選び方など
- 2024年11月22日事業承継のマッチング支援とは?利用するメリット・デメリットなど
- 2024年11月1日事業承継と廃業はどちらを選ぶべき?それぞれのメリット・デメリットなど
- 2024年10月25日経営承継円滑化法とは?事業承継で活用できる支援制度をわかりやすく解説
- 2024年10月11日事業承継における11の失敗事例|原因や成功させるポイントを詳しく解説
- 2024年9月20日事業譲渡における従業員への影響|退職金の扱いや注意点などを詳しく解説
- 2024年7月5日事業承継ガイドラインとは?概要や策定の背景をわかりやすく解説
- 2024年6月14日農業を事業承継するには?方法や成功に導くためのポイントを解説
- 2024年6月7日事業承継の計画について|策定の手順・ポイントや計画書の書き方
- 2024年5月31日事業承継における中小企業の現状や課題は?解決策とともに弁護士が解説
- 2024年5月24日事業承継のための融資「事業承継ローン」の種類や利用の流れについて
- 2024年5月2日相続対策としての事業承継|事業承継税制などの相続税対策も解説
カテゴリー一覧
タグ